文●沢村慎太朗(Believe Japan 特約記者)
大都市に暮らすひとは知らないかもしれない。でも自然と共に生きていくような土地で暮らすひとは、たぶんその姿に馴染みがあるはずだ。スズキがセニアカーという商品を販売している。年に万の位の数を売るほどの隠れたヒット作だ。価格は30万円台で、30万円を切るものもある。セニアカーは、このサイトの主記事になっている福祉車両よりもビジネス的にだけ見れば小さな存在である。だが、それは行政や法律が組み上げた今日の日本の社会の仕組みがカバーしきれていないところを補う救いの手でもあるのだ。
それはどんな機械なのか?
長さが1mちょっとで、幅のその半分くらいの床板の四隅にタイヤを配する。
その床板の後ろ寄りに、ひとり用の簡単なイスを載せる。
椅子の下には電池を置く。
後ろ2輪の軸にモーターを組み込んで、電池から流れてくる電気でこれを駆動する。
前2輪には首を振るシカケが織り込まれていて、それによって曲がることができる。
ゴルフ場などで電動カートに乗ったことがあるかもしれない。それは、そんな電動カートを思い切り小さくして一人乗りにしたようなクルマなのだ。ただし電動カートと違うところもある。
前輪を切るのは、自動車のような丸型のハンドルじゃなく、イスの前に立ちあがったバーループ型のそれだ。言い添えれば、ちゃんとサスペンションもついている。
走るための操作はアクセルを踏むのじゃなく、バーループ型ハンドルについているレバーを押し下げる。押し下げると前へ進む。離すとブレーキがかかる。ちなみにスイッチを切り替えればバックもできる。
これと別にブレーキレバーもついているが、それは自動車でいうパーキングブレーキとして機能する。バー型ハンドルから上に左右のバックミラーが生えている。
そのバー型ハンドルの前に荷物を入れるカゴが取り付けられているものもある。
見方を変えれば、それは電動スクーターをふたつ並べて4輪車にしたようにも思えるかもしれない。
それは行政と法律の中で、どんな立ち位置なのか?
日本は法治国家である。国民は幸せに生きる権利をもつとともに、皆がうまくやっていくために、ある程度の縛りがかけられる。その縛りを決めているのが法律だ。だから、皆が使う公共の道路での振舞いについては道路交通法という法律が定められている。たとえば赤信号を無視して交差点を渡ってしまうのは、自動車やバイクだけじゃなく、自転車でも歩行者でも法律違反だ。自転車でも酔っ払い運転をしたら法律違反なのだ。人間の自力じゃなく、モーターやエンジンなどの力を借りて動くような機械は、ともすれば凶器になるかもしれないから、その機械のあれこれを決める法律も定められた。運転する人間に対して免許という形で能力の足切りをすることもある。セニアカーには車検もナンバープレートもないけれど、やはりこうした決め事の内側にいる。
道路交通法では、それは電動車いすの仲間とされている。車いすは2000年前の三国志にも描かれていたくらい歴史は古いが、そこに馬力を発生する原動機をとりつけて自走できるようにしたものが生まれたのは今から100年ほど前だ。
言うまでもなく、それは身体が不自由なひとのための機械である。それゆえに、道路交通法では歩行者と同じ扱いになっている。
セニアカーは、電動車いすよりもずっと仕掛けが大振りだけれど、法律上はやはりその一種という扱いになっているのだ。
ちなみに道路交通法は、そのメカも規定している。
たとえば、長さは120cmで、幅は70cm、高さは109cm。
推進力を生む原動機はエンジンはダメでモーターだけ。
しかも、出せる最高速度は時速6km以下に限定されている。
人間の歩く速さは、のんびり歩いて時速3kmで、仕事に行くときみたいに真面目に歩いて時速4km~5km。ウォーキングのような速歩きで時速6kmくらい。だから歩行者としてセニアカーを扱うならば、時速6km以下にしたほうがいいとされたわけだ。
ちなみに、現在のJIS(日本工業規格)は、電動車いすとセニアカーを、ハンドルの形で区分けしているようだ。電動車いすの場合は、手元に取りつけられた小さな棒型(ジョイスティック)の操作を電子制御で前輪の操向に置き換えて曲がる。これをジョイスティック型と分類する。一方で、セニアカーのようにバー型ハンドルで向きを変えるものをハンドル型と分類。こちらには3輪のものと4輪のものがあるので、その区別もしている。
どんなひとが使ってるのか?
いま書いたように、セニアカーは、身体が不自由なひとのために生まれた電動車いすの仲間として扱われている。だけれど、身体が不自由といっても、いろいろな不自由がある。身体障害者福祉法が定めた1級から6級までの重い不自由をもつひともいる。そこまでじゃないけれど、膝が悪くて立ったりしゃがんだり遠くまで歩いたりすることが苦痛というひともいる。歳を取ればだれでも、どこかしら身体にちょっとした不具合は出るものだ。セニアカーに乗っているのはそういうひと。達者に暮らしてはいる。けれど、若いころのように出歩くほどの元気はなくなってきた。でもだれかの世話にならず自力で気ままに買い物に行ったり散歩したりしたい。そんなお年寄りがセニアカーに乗っているのだ。スズキによれば、80歳以上のひとが3/4を占めるという。男女比率は6:4で男性の方が多いそうだ。
セニアカーはいつ生まれて、どのように育ったのか?
出発点である電動車いすは、1964年の東京オリンピックのときに日本で外国製のそれを目にしてから認識が一般化し、国内のあちこちで作られるようになって、1977年にはJIS(日本工業規格)でも規格が定められるようになった。
スズキは、その少し前の1974年に最初の製品を発売している。
以降、彼らはそれを少しずつリファインしていくのだが、その中で1985年にセニアカーという商標で呼ぶものが生まれた。
これはまだ3輪で作りも簡素だったが、身体の衰えを感じていたお年寄りに好評で、以降スズキはこのセニアカーを継続して開発し販売していくことになる。
現行ラインアップは、タウンカートと呼ばれる街乗り向きの小柄なものを含めて3車種(この他に電動車いすも販売中)。ちなみに、セニアカーと同じ立ち位置のハンドル型の4輪型は、ヤマハやホンダといった2輪メーカーも、やはり市販しており、トヨタ車体やクボタなど自動車や2輪車に関連があるメーカーもそれに加わっている。
では、それらハンドル型は、どのくらい売れたのか。
電動車いす安全普及協会という業界団体が発表している出荷台数の資料によるとこんな具合だ。
スズキが端緒を切った1985年は年に1000台。これが1990年には1万のラインを越して、1999年には2.4万台弱にまで伸びている。ここまでは3輪だ。翌2000年には4輪型が加わって、それによって3輪の台数が減ったものの、全体では伸びて3万のラインを窺うようになる。以降2005年まで2万数千台を堅持する。
しかし、2006年からは2万のラインを切って、昨2016年では1万4846台となっている(言い添えれば、ジョイスティック型の電動車いすは、この20年ほど年に6000台前後で推移している)。
というわけで、俯瞰すれば、2000年から数年ほどピークを描き、以降は下降に転じて、ちょうど下がりどまったような按配だ。
これについて、スズキは、件のピークは介護保険法が施行されるようになり、参入してきたレンタル事業者が一斉に買ったために、一種の特需が形成されたとの認識を示している。このファクターを除いてしまえば、年1万数千台をキープする堅調だといえる。
機構がシンプルなセニアカーは耐用年数もおそらく10年以上だろうと予想する。とすれば、ユーザーの数は年に1万人のペースで増えているということになる。この10年だけの出荷台数で大雑把に考えてみても、15万台ほどが稼働している計算になる。
セニアカーで考えておかねばいけないこと
セニアカーは4輪だが、つくりは2輪車に近い。バイクと違ってヘルメットも義務化されていない。また、各メーカーは転倒しないように斜面で大丈夫な角度を明示したりしているが、セニアカーが使われるのはきちんと舗装された道路ばかりではなく、轍や凸凹がある畦道など未舗装路も多い。また、最高速が時速6km以下に制限されているとはいっても、重いバッテリーやモーターを積むから車重は100kg級になる車種も多い。これに乗員の体重を加えたマスが走るのだから、人間に接触したときのダメージは少なくないだろう。しかも、運転者の多くは機敏な若者ではない。こういう潜在するリスクに対して、たとえばスズキはアクセルレバーを目一杯握るとブレーキが掛かって停まる。初期は二輪車からの乗り換えが多かったので、ブレーキと間違えて握りしめることを想定したような機能を組み込んだり、制限速度をさらに下げるリミッターを加えたりと工夫を重ねているが、乗るひとには安全に十分気をつけて自由で快適な移動を楽しんでいただきたい。
またスズキは、運転者だけでなく対人や対物までカバーする専用の保険も用意し、より安心して使ってもらえるようにサポートしている。
これからの日本におけるセニアカーの意味
いまや日本は高齢化社会だ。国は65歳から74歳までを前期高齢者と呼ぶが、その65歳以上の人口は今や全国民の3割近くになっている。歳をとれば、大きな病 気や怪我もなく、身体の不自由がなくても、だれでも動くのが辛くなる。あまりに動かないでいると、どうしても気持ちが鬱屈しがちになる。それで済めばまだしも、物理的な問題も生まれる。
数少ない大都市圏を除けば、生活インフラがロードサイド店に集中するようになってしまった。そこまで行かなくても、街の商店街は軒並みシャッターを下ろして崩壊し、隣近所に八百屋や魚屋がある状況は夢物語になりつつある。公共交通機関は経営合理化の圧力によって、人口が少なくて利用者が少ない路線をどんどん廃線にしていく。近くにコンビニでもあったら幸いで、食べ物の調達すら大変という状況が起きている。
日本は戦後に自動車社会を選択してしまった。それがもたらした一種の必然でもある 。自動車を運転できれば、それで何とかなる。しかし、自動車の運転が覚束なくなったら……。
警察が交通関係について今もっとも憂慮しているのは、運転スキルが下がった老人が起こす事故の問題だという。だから警察は高齢者が自ら免許の返納を促すように舵を切った。だが、免許を返納して自家用車に乗れなくなってしまえば、動くのが辛くなってきた身体では移動することが大仕事だ。
こういうひとたちの受け皿にセニアカーがなっているのだ。
スズキによると、セニアカーのユーザーのうち、独居老人は2割強で、配偶者だけと同居する例は5割強。つまり、 3/4が同居する若い者に買い物などの用足しを頼むことができず、自力でなんとかしなければいけない状況に直面したひとがセニアカーに頼っているのである。また、いまやセニアカー購入者の半分が免許を返納したお年寄りだという。で、返納して困ってからではなく、そのまえに購入する例も増えているという。
セニアカーに代表される「ハンドル型の電動車いす」は、着実に販売台数を重ねている。なのに、初めて耳にしたら何だか分りにくそうな呼び名しか与えられていない。本来の意味からすれば、それは道交法やJISが定める身体障害者のための介護機器と、ミニマムトランスポータ—のあいだに位置する移動機械である。
国土交通省は2012年に、高速道路ではない一般道だけを走 り、軽自動車よりも小さな2人乗りのクルマを「超小型モビリティ」として導入する方向を示した。だが、それは自動車の範囲を下に広げるだけのものであり、セニアカーが受け持っている領域はカバーできない。それは、ここまで読んでくださった皆さんには自明だろう。
その現実に応えて、困っているひとたちがそこに沢山いたからスズキはセニアカーを作った。
セニアカーのような移動ツールに対する需要は、これからさらに拡大していくだろう。過疎地だけの、地方都市だけの問題ではない。首都圏の住宅地でも同じような状況は生まれつつある。現在はプレミアムセダンに乗るひとや健康のためといって自転車で遠くまで走るひと、そういうひとたちだってセニアカーの現実は、 ほどなく目の前にやってくる「リアル」なのだ。
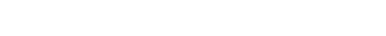


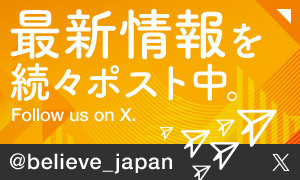







No Comments