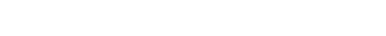文●石井昌道 写真●Believe Japan 2022/3/11(金)配信 ホンダは手動運転補助装置付き自動車のテックマチックシステムを1976年、足動運転補助装置付き自動車のフランツシステムを1982年に発売を開始している。手動運転補助装置付き自動車は他メーカーのモデルも含めて複数回の試乗経験があり、いまではスムーズに運転できるようになっているが、昨秋に初めて試乗したフランツシステムは少し戸惑った。右足によるアクセルとブレーキのペダル操作は何の問題もないものの、ウインカーなどのスイッチ操作も兼任しなくてはならない。また、左足によるハンドル操作は、普段はあまり使わない動きだったこともあって慣れるのに時間がかかった。 今回は2回目の試乗。操作方法はわかっているうえ、左足の動かし方もイメージできていたので、落ち着いて走りだすことができた。 まず、乗り込むには右足のつま先をドアノブに引っかけてドアを開けながら、身体を入れ込めるようにある程度は手前に引いていかなければならないのだが、これがまた難しい。片足立ちで不安定になってしまう。ただし、フランツシステムを相棒にしようと本気で挑む人のほとんどは、こういった操作には慣れていて難なくこなしてしまうそうだ。 試乗車はオプションのパッシブシートベルトが装備されているので、シートに座れば自動的にシートベルトが装着できる。 無事にシートに収まった後に走り出すには、まずシステム始動およびシフトレバーを操作するために、ブレーキペダルを踏み続けた状態にする必要がある。そのために、ブレーキペダル上方にロック用ボタンがあり、これを押しながらペダルを踏み込めばロック状態に。そして右足でPOWERボタンを押し込んでシステムが始動。そのまま、足用シフトペダルでDレンジを選択し、ブレーキ・ロックを解除すれば走り出せる。 現行フィットは電子制御パーキングブレーキが採用されているので、ブレーキ・ロックを解除しても停止したままだが、アクセル・ペダルを操作することで自動解除され、クリープで動きだす。アクセルとブレーキの操作は、ノーマル車両と同様なので何も問題ない。 ハンドル操作は左足で、自転車のペダルのように縦回転させて行う。下に押し込むときは力が入りやすいが、上に引き上げるときはちょっとだけやりづらさがある。普段はあまり使わない筋肉を動かしているからだが、これは慣れの問題であり、2回目の試乗で勝手はわかっていたので、今回は戸惑いがほとんどなかった。 前回は、普段は手でハンドル操作している自分にとって、足による操作は大雑把になってしまうのではないかという心配があって慎重になりすぎ、それが操作遅れを誘発していた。また、四つ角を曲がるときやUターンのときなど、ハンドル操作量が多いときにも慎重だったので操作が遅かったが、今回は緩いカーブでは繊細に、操作量が多いときは大胆にとメリハリをつけるようにしていったら、上手に動かせるようになり、クルマとの一体感がでてきた。操るのが楽しいと感じられるようになったのだ。 運転しながら足用コンビネーションスイッチを操作することもマスターしなくてはならない。頻繁に使うウインカーは、慣れてくれば左はつま先でブレーキペダルを踏みながらかかとでポンッと押し込めるので楽に操作できる。MTでスポーツ走行するときのヒール&トーと同じ要領だ。ところが右は距離が離れているのでブレーキペダルを踏みながらの操作は無理。道路交通法では右左折や転回する地点の30メートル手前でウインカーを点滅させることになっているので、右折時にはアクセルペダルもブレーキペダルも操作しない空走状態で右足でウインカースイッチを押し込む必要が出てくる。余裕があれば可能だが、そうではないシチュエーションも出てくる。そんなときは交差点で一時停止してブレーキ・ロックを使い、ウインカーを操作、ブレーキ・ロック解除して走りだすことになる。自車を安全に走らせるには仕方ない緊急回避だろう。手順はちょっと煩わしく、最初のうちは頭で考えながらゆっくりと操作していたが、慣れてくるとほぼ無意識で素早く操作できるようになった。 足用コンビネーションスイッチは、個々のドライバーの好みや操作のしやすさに合わせて9パターンが用意されており、購入時に選択できるようになっている。 2回目の試乗にして、早くも慣れてきてフランツシステムが頼もしい相棒になってきた。ノーマルの市販車をベースにモディファイしたシステムなので、すべてが完璧というわけではないが、自らの意志で移動の自由を獲得したい、運転の喜びを味わいたいという思いが強ければ、問題なく使いこなせるだろう。安全運転を支援するHonda SENSINGも性能が向上してきているので心強い(過信は禁物だが)。運転操作を覚えるのに多少のハードルはあるが、マスターしたときの喜び、得られる価値は大きいはずだ。 自動車ジャーナリスト 石井昌道 内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)自動運転にも参加する自動車ジャーナリスト。幅広い視野と知見で的確な評論を行う。 ※撮影車両には、一部オプション装備が含まれています。 ホンダ... ...
On 2022年3月11日 / By wpmaster文●石井昌道 写真●Believe Japan 2022/1/13(木)配信 視覚障がい者の単独歩行を支援するナビゲーションシステムの「あしらせ」。靴に装着する振動デバイスと独自のスマートフォン用アプリで構成され、目的地を設定して歩行を開始すると、足の甲やかかと側面などが振動して、曲がり角が近づいたこと、左右どちらに曲がるのか、などを知らせてくれる。2022年度中の販売開始を目指して開発・実証中だが、今回はそのプロトタイプを体験した。 振動デバイスは普通のスニーカーなどに簡単に装着できて、そのまま脱いだり履いたりも可能。履き心地にも違和感はない。 スマートフォンのアプリで目的地を設定して歩き出すと直進時には両足のつまさきに近い甲が一定間隔で振動して、ルート上を正常に歩いていることが伝わってくる。曲がり角に近づくと甲、かかと、側面のすべてが振動し、一旦立ち止まるように促してくる。停止すると、右に曲がるならば右側の側面が振動してルートを知らせてくれる。振動はかなりわかりやすく、これなら気付かないなんてことはないだろう。音声で知らせるナビゲーションシステムはあるが、聴覚は歩行時の安全確保にとって重要であり、注意を削がれる可能性もある。足に振動で伝えることはそういった心配がなく、また、直進、停止、左右に曲がるなどの情報が直感的にわかり、有効なシステムだとわかった。 スマートフォンの地図アプリを歩行時に使う人は多いだろうが、GPSの誤差があったり、目的地設定したらとりあえずどちらに進めばいいのかわかりにくいという経験をしていることだろう。そういった悩みを解消すべく、独自のアルゴリズムを開発しているのも「あしらせ」の特徴だ。振動デバイスにはモーションセンサー電子コンバスが付属しており、歩いて移動するとその情報をアプリにフィードバック。誤差などを修正して誘導情報生成が行われている。自動車用カーナビが、クルマのタイヤ回転センサーなどを利用して自車位置を推定してGPS情報の誤差を修正しているのと同じ考え方だ。もともと「あしらせ」はホンダの新事業創出プログラムから生まれただけあって、自動車メーカーのノウハウが生かされているのだ。 自動車ジャーナリスト 石井昌道 内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)自動運転にも参加する自動車ジャーナリスト。幅広い視野と知見で的確な評論を行う。 関連記事:足の感覚で歩行をサポート! 視覚障がい者向けナビゲーションシステム「あしらせ」 ...
On 2022年1月13日 / By wpmaster文●石井昌道 写真●Believe Japan 2022/1/12(水)配信 翔(KAKERU)はホンダの最新車いすレーサー(陸上競技用車いす)。いかにも競技用といった無駄のない機能美に目を惹かれるが、ここにたどり着くまでには長い歴史があった。 1981年に障がいのある人たちの社会的自立の促進を理念としてホンダ太陽(本田技研工業の特例子会社)が設立され、そこに所属する障がい者スポーツのトップアスリートによって1999年にホンダアスリートクラブが発足。翌年には本田技術研究所が車いすレーサーの開発に取り組み始めた。2002年からは毎年新しいモデルを投入して競技を続け、2013年には八千代工業が参加することで量産体制が整う。2014年の極(KIWAMI)、翌年の挑(IDOMI)などを経て、20年の集大成となったのが翔(KAKERU)なのだ。 ウイング形状のメインフレームやホイールなどフルカーボン製で、直進性を保つステアリングのダンパーをフレーム内に収めたビルトイン・ダンパーステアリングが特徴。ルックスも美しくなり、グッドデザイン賞を受賞している。価格は383万円(塗装あり/税別)とプレミアムコンパクトカー並みだ。 今回試乗させてもらったのは前モデルの挑(IDOMI)で、ビルトイン・ダンパーステアリングではないものの、バリバリの競技用で貴重な体験だった。まず、注意深く乗り込む必要がある。胸が太ももにぴったりとくっつくぐらいの前のめりの姿勢でバランスするようにできているため、普通に起き上がった姿勢で腰掛けると簡単に後ろにひっくり返るからだ。 ただ走らせるだけなら、それほど難しいことはない。一般的な車いすと同じようにホイールのハンドリムに手をかけて回せばいい。ただし、発進時にはハンドリムはかなり重く感じる。速く走るために、少ない操作でもホイールがたくさん回るようハンドリムが小径だからだ。発進してある程度まで速度がのってくると快適。さすがは競技用で走行抵抗が少なく、惰性で気持ちよく転がっていく。自分なりに感じたコツとしては、ハンドリムを操作するときは、短いストロークのなかで一気にトルクをかけること。こうするとグンッとスピードアップが図れる。ステアリングはダンパーによって直進状態が保たれるようになっていて、惰性走行のときに進路修正を図りながら進んでいく。 腕が疲れるのはもちろん、進路を見るために頭を上げるから首も疲れる。前のめりの姿勢を維持するのも意外や大変で、これでマラソン競技をするアスリートをリスペクトする気持ちが生まれた。それでも、信じられないほど軽量・高剛性で走行抵抗の少ない本物の競技用車いすレーサーを走らせることは、この上なく気持ちいい体験だった。プロの道具の凄さを知って贅沢な気分になれたのだ。 自動車ジャーナリスト 石井昌道 内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)自動運転にも参加する自動車ジャーナリスト。幅広い視野と知見で的確な評論を行う。 ...
On 2022年1月12日 / By wpmaster文と写真●Believe Japan 2021/11/13(土)配信 11月10日~12日にお台場で開催された国際福祉機器展で、おもしろい1台を発見したのでご紹介したい。それは、ホンダN-VANをベースにした「車いす移動車」のコンセプトモデル。制作したのは、身体障がい者用の自動車運転装置(フジコン)を長年開発し続けているフジオート。これまでも運転でハンディになる部分を補う各種装置(手動装置/左アクセル/ステアリンググリップ/左ウインカー/右ワイパー/シフトレバー/アシストグリップ/延長ペダル/足動装置など)を市場に送り出している、福祉車両装置開発の老舗だ。 今回のN-VANコンセプトのポイントは以下の3つ。 【車いすのひとが一人で運転できる自操式車両であること】 車いすに乗ったまま運転席の近くまで移動。車内で運転席に移乗して、自身で運転できる仕様となっている。バックドアに備わる電動リフトから、リモコンを使って乗り込むという設計だ。そして、助手席の位置まで車いすで移動し、運転席に移乗。展示車両は移乗のしやすさを重視して。コラムタイプの手動運転装置が取り付けられていた。 【軽自動車のリフト付き車いす移動車であること】 プラットフォーム長1000mmの専用小型リフト(耐荷重150kg)を開発。定員は4名(運転席、助手席、右セカンドシート、車いす)、実際に車いすのひとが運転する場合は3名となることを想定。 【避難時仕様であること】 昨今の非常時に備え、車いすのひとが一時的に避難したいときに少しの間生活できるような装備を設置。テントや簡易トイレ、机、ドリンクホルダー、小型シンクなどが備わっている。 「キャンピングカーブームや優れたユーティリティを誇るN-VANからヒントを得ました。今回この福祉機器展でみなさんにさまざまな意見や感想を伺い、将来的に販売を実現していきたいです」と話を伺った。 まだコンセプトモデルのため具体的な車両価格は出ていないが、リフトの搭載費用として改造費80万円~となるとのこと。いづれにしても、見ているだけで、話を聞いているだけでワクワクさせてくれる1台だった。 フジコン公式サイトhttps://www.fujicon.co.jp ...
On 2021年11月13日 / By wpmaster2021/11/9(火)配信 Hondaは福祉車両をはじめ、福祉のさまざまな取り組みを紹介し、実際に体感できるイベント「HondaハートJoy for Everyone」を、11月9日(火)から30日(火)まで「Hondaウエルカムプラザ青山」にて開催すると発表した。 今回のイベントは、Hondaの創業時からの基本理念”人間尊重”の考え方のもと、“誰もが気持ちよく、楽しく乗れるクルマづくりをすすめるとともに、身体の不自由な方々が活躍できる機会や場の拡大をサポートする”という想いから企画されたという。Hondaのこれまでの取り組みを紹介するとともに、福祉領域における製品展示などを通じて一般のひとに実体験してもらうことで、Hondaの取り組みをより深く知ってもらおうというイベントだ。 【イベントでの出展品】 国内唯一である足動運転補助装置「Honda・フランツシステム」 1965年にドイツで開発されて以来、ヨーロッパで高い評価を得てきたフランツシステムは、両上肢が不自由な方が両足だけで運転操作できる運転補助装置。Hondaは1981年に開発者のフランツ氏から直接技術指導を受け、さらに独自の技術を加えて1982年に国内で初めて販売。現在、国内で唯一フランツシステムの開発・販売を行なっている。 視覚障がい者の単独歩行を支援する、シューズイン型ナビゲーションシステム「あしらせ」 「あしらせ」は、視覚障がい者の単独歩行を支援するシューズイン型のナビゲーションシステム。Honda新事業創出プログラム「IGNITION(イグニッション)」発のベンチャー企業第1号の株式会社Ashirase(あしらせ)で、2022年度中の販売開始を目指し現在開発が進められている。スマートフォンアプリにでの音声入力や案内、加えて靴につける振動インターフェースで構成され、聴覚、手の次に知覚しやすい足への振動により、向かう方向を直感的に示すことを可能としている。 2021年度グッドデザイン賞を受賞した、陸上競技用車いす「翔(KAKERU)」 ”勝利の笑顔をアスリートに届ける”をコンセプトに、ホンダの最新テクノロジーを結集させて開発された「翔(KAKERU)」は、ウイング形状のメインフレーム等は、F1やHonda Jetで培ったカーボンファイバー技術の知見を採用。アスリートが「これに乗って頑張りたい」と闘志を燃やせるデザイン、仕様を目指したもので、「2021年度グッドデザイン賞」(主催:公益財団法人日本デザイン振興会)において、グッドデザイン賞を受賞した。すで幾多の戦績を残している。 【開催概要】 イベント名:「HondaハートJoy for Everyone」開催概要開催期間:2021年11月9日(火)~30日(火)開催場所:「Hondaウエルカムプラザ青山」(東京都港区南青山2丁目1−1 Honda青山ビル 1階)概要:Hondaの福祉のさまざまな取り組みや製品が体感できる展示イベント展示内容:・視覚障がい者の単独歩行を支援 シューズイン型のナビゲーションシステム「あしらせ」・陸上競技用車いす フラッグシップモデル「翔(KAKERU)」・国内唯一となる両上肢の不自由な方が両足だけで運転操作可能な運転補助装置「Honda・フランツシステム」(車種:FIT)・手足の不自由な方のための運転補助装置「Hondaテックマチックシステム」(車種:FIT)・助手席リフトアップシート車(車種:FREED)、車いす仕様車(車種:N-BOX)他 ...
On 2021年11月9日 / By wpmaster文●Believe Japan 写真●ホンダ 2021/3/9(火)配信 今日、「家族に高齢者がいる」、「乗り降りがしんどい」など、アクセスが便利なクルマを必要としている潜在的なユーザーは少なくない。それに応えるビリーヴカー(福祉車両)は、設定車種が大幅に拡大され、趣味やライフスタイルに合った車種選びも可能になってきている。しかし、買い替えコストや「自身で歩くことができる」などの状況によって、ビリーヴカーを購入するまでに至らないケースもあるだろう。多くの場合は、できれば後付けのパーツで、手軽にクルマを便利で安心なものにしたいと考えているのではないだろうか。 アクセサリーといえば、エアロやアルミホイール、LEDランプなどドレスアップ方向のパーツをイメージしがちだが、じつは高齢者にやさしいパーツがたくさんあるのをご存知だろうか? これらのパーツは、高齢の家族と暮らしていればもちろん、そうではなくても、広く一般的に使えるアクセサリーであったりする。手軽なカスタムを可能にするアクセサリーには数々の製品がラインアップされている。今回はその中から、ホンダ車に注目。実際にどのようなアクセサリーがあるのか見てみたいと思う。 幅広い年代のファミリー層から高い人気を集める「N-BOX」や「フリード」、「ステップワゴン」、そして「オデッセイ」には高齢者ユーザーのクルマ移動を快適にしてくれるアクセサリーが豊富に用意されている。 つかめる安心感 足もとに不安があると、どこかにつかまる必要がある。ビリーヴカーでは、一般車にはない場所にさまざまなグリップが取り付けられている。あらゆるタイプがあるが、ここでは代表的なものを一部紹介する。 [シートバックグリップ(N-BOX、フリード、ステップワゴン )] 横に広くつかみやすいタイプの乗降用「シートバックグリップ」は、乗り降り時と車内での移動に便利だ。アクセスを簡単で安全にしてくれる。価格は1万780円(税込み)。 [フロアグリップ(フリード、ステップワゴン)] 助手席の座面横に取り付けられた「フロアグリップ」は、しっかりとつかむことができ、クルマの乗降時に加え、走行中の姿勢安定にも効果を発揮する。多くの人にとって便利な優れものである。本体とグリップパッドの合計価格は2万6950円(税込み)。 [吊革グリップ(N-BOX、フリード、ステップワゴン、オデッセイ )] 山道を走行する時など、後席に座る人は上半身を前に乗り出し、サイドウインドウの上に取り付けられたグリップをつかんでいることが多い。ところが、体格や年齢などによっては、腕を上げている姿勢はかなりの負担になることもある。そこで、通常のグリップを「吊革(つりかわ)」タイプにしてしまうアクセサリーが「吊革グリップ」だ。腕を高く上げる必要がなく、ラクな姿勢でしっかりと握ることができる。使用しないときは巻き上げ可能で、視界の邪魔にならない。価格は5280円(税込み)。 [ドリンクホルダーグリップ(フリード、ステップワゴン)] ダッシュボードのドア側に設置されたドリンクホルダーは、丁度よい取手としてつかみながら車内に乗り込む場合もあるが、これをつかみやすい「グリップ」にしてしまうアクセサリーがある。腕を上げなくても手がかけられる高さにある「ドリンクホルダーグリップ」は、価格は9350円(税込み)。 みんなに優しい装備 高齢者や歩行困難な方だけでなく、多くの人にとっても「あれば便利」なアクセサリーもある。 [テールゲートストラップ(N-BOX、フリード、ステップワゴン、オデッセイ )] 車高が高めのクルマの場合、リヤゲートを開けるのは問題ないが、閉めるときにドアが届かないという場合がある。つかみやすく、ラクに閉められる「テールゲートストラップ」は背が届かない、腕を上げにくいといったユーザーにとって優しいアクセサリーだ。価格は1100円(税込み)。... ...
On 2021年3月9日 / By wpmaster文と写真●Believe Japan 2021/2/15(月)配信 大幅マイナーチェンジしたホンダ オデッセイの「サイドリフトアップシート車」を体験試乗! 新型オデッセイの上質感とゆとりのある空間を、実際に試乗しながらご紹介します。 関連記事:【新型オデッセイ試乗】回転シート車は、これからのクルマ選びにハズせない! ...
On 2021年2月15日 / By wpmaster文と写真●Believe Japan 2021/2/12(金)配信 ホンダの上級ミニバン「オデッセイ」が、昨年末に大幅マイナーチェンジを実施。それにともない、車いす利用の方や足腰の弱い高齢の方に便利な「サイドリフトアップシート車」と「助手席リフトアップシート車」も新しくなった。 新型オデッセイが目指したのは、『さらなる上質さと心地よさの向上』。厚みのあるフロントマスクの採用で外観はグッと迫力を増したが、むしろ注目すべきは、既存ユーザーから徹底的にヒアリングを行い見直したという、その中身だろう。 たとえば、インテリアではインパネまわりが全面的に変更され、ナビゲーションパネルの大型化(10インチ)やコンビメーターの形状変更、手の触れやすい位置へのソフトパッドの配置、収納式ドリンクホルダーの追加、インパネアッパーボックスをリッド付きにするなど、ユーザー目線で変更されている。 また、静粛性を高めるべくフロントドアガラス/スライドドアガラスの遮音化、テールゲートガラスの板厚アップに加え、ノイズリデューシングホイールも採用するという徹底ぶり。安全運転支援システム「ホンダセンシング」では、後方誤発進抑制機能が新たに加わった。 オデッセイの回転シート車には、「サイドリフトアップシート車」と「助手席リフトアップシート車」があるが、これは車いす利用の方(もしくは足腰の弱い高齢の方)がどちらに座って移動したいかで決まることが多いという。つまり、家族内で相談しましょうというわけだ。ユーザー目線で言えば、選べるところがありがたい。 今回試乗したのは、新たにアブソルートに設定され、2.4Lガソリンエンジンを搭載した「サイドリフトアップシート車」。市街地、高速道に加え、ちょっとした山道でも試したが、全行程でドライバー、2列目シートとも落ち着いて乗れる1台に仕上がっていた。この「落ち着いて乗れる」ことは、通常のクルマに加えてビリーヴカー(福祉車両)にとっても非常に重要なチェック項目。リラックスできる環境であれば、おのずと笑顔も増えるもの。 現在、この車格で選べるビリーヴカーはさすがに少ない。快適性の話はベースとなるクルマそのものに起因する話ではあるが、今回改めて、車いす利用の方や足腰の弱い高齢の方に、オデッセイはやさしいクルマだと感じた。 ホンダ オデッセイ アブソルート サイドリフトアップシート車 FF/7人乗り(CVT) ■全長×全幅×全高:4855×1820×1695mm■ホイールベース:2900mm■トレッド前/後:1560/1560mm■車両重量:1830kg■エンジン:直4DOHC■排気量:2356cc■最高出力:175ps/6200rpm■最大トルク:23.0kgm/4000rpm■サスペンション前/後:マクファーソン式/車軸式■ブレーキ前/後:Vディスク/ディスク■タイヤ前/後:215/60R17 ■車両価格:363万4000円(消費税非課税) 関連リンク:ホンダ福祉車両(https://www.honda.co.jp/welfare/) ...
On 2021年2月12日 / By wpmaster文●Believe Japan 写真●Honda、Believe Japan 2020/12/29(火)配信 「主に筆談だった聴覚障がいのある従業員と健聴者のコミュニケーションを、より円滑にできないものか……」。かねてからこの課題に直面していたHonda。発表された「ホンダ・コミュニケーション・アシスタンス・システム(以下Honda CAシステム)」は、Hondaの先端科学技術の研究を担う、株式会社ホンダ・リサーチ・インスティチュート・ジャパンとホンダ太陽株式会社、ホンダR&D太陽株式会社が共同開発したもので、社内利用が2020年9月から本格的に開始されたとして、今回報道陣に披露された。 会議の場などリアルタイムに双方向のコミュニケーションが求められる状況では、意思疎通の正確性、そしてスピードなど、多くの課題があるもの。このHonda CAシステムは、発話内容をリアルタイムかつ高い正確性でテキスト表示することができ、会議の流れやコニュニケーションを妨げることがない。 マイク、音声認識サーバー、テキスト配信PC、テキスト表示用タブレット・スマートフォン等で構成されているHonda CAシステムは、発言者がマイクに向かって発言すると、AI音声認識システムが発話内容をテキストに変換、テキスト配信PCを通じてタブレットやスマートフォンにテキスト表示するもの。社内業務を考慮したチューニングで、社内専門用語も高い正確性をもって変換可能で、発話から表示までの時間も約2秒と素早い。また、音声認識に加えて、キーボード入力や手書き入力でも発言可能で、図面やイラストなども表示することができる。 現場ではすでに「筆談負荷が大幅に減り、会議に集中できる」、「リアルタイムに理解でき、タイミングよく意見を主張できるので、会議参加の実感が得られ、モチベーションにつながる」、「仕事の経緯が分かるので、納得して仕事に取り組める」などと高評価。会議時間も2~3割短縮される効果も確認できているという。 「技術は人のためにある」。このHondaの研究開発の信念が具現化したHonda CAシステムは、現在はHonda内での活用にかぎられているが、今後、さまざまな状況に使用される可能性を秘めたシステムといえるだろう。 本田技研工業株式会社 人事部 多様性推進室室長 町 潤 氏 Hondaの基本理念である「人間尊重」は、自立した個性を尊重しあい、平等な関係に立ち、信頼し、持てる力を尽くすことで共に喜びをわかちあいたいという理念(自立、平等、信頼)で成り立っていると町潤氏。 ホンダ・リサーチ・インスティチュート・ジャパンプリンシパルエンジニア 住田直亮 氏 今後も、すべての人々が働きやすい環境をつくるべく「完全ハンズフリー音声入力」、「自動学習・自動登録」、「図表入力、変換」、「手話認識・生成」などの展開を実現したいと住田直亮氏。 ...
On 2020年12月29日 / By wpmaster文と写真●Believe Japan 2020/9/11(金)配信 介助する側、介助される側、双方の立場になってビリーヴカー(福祉車両)をインプレッション! レポートするのは、介護経験があり自身も福祉車輌取扱士スペシャリスト資格を持つタレント・モータージャーナリスト 竹岡 圭。今回は、手動運転補助装置「Honda・テックマチックシステム」搭載の新型フィットをご紹介します。 ホンダ福祉車両:https://www.honda.co.jp/welfare/ ...
On 2020年9月11日 / By wpmaster© 2016-2020 Believe Japan, Inc. All rights reserved.