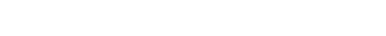文と写真●Believe Japan 2024/8/23(金)配信 介助する側、介助される側、双方の立場になってビリーヴカー(福祉車両)をインプレッション! レポートするのは、介護経験があり自身も福祉車輌取扱士の資格を持つタレント・モータージャーナリスト 竹岡 圭。今回はホンダ フリード e:HEV CROSSTAR スロープを実際に試乗しながらレポートします。 ...
On 2024年8月23日 / By wpmaster文と写真⚫︎Beleave Japan 2023/11/17(金)配信 先ごろフルモデルチェンジしたホンダ N-BOX。そのスロープ車に触れることができたので報告したい。 N-BOXは、軽四輪車新車販売台数で8年連続(2015年〜2022年度)で第一位を獲得するなど、その優れた資質で多くのユーザーに支持されてきた。 3代目となる新型は、これまで評価されてきた内容をさらにブラッシュアップ。エクステリアはより上品なたたずまいとなるように手が加えられ、テールゲートハンドルを70mm(スロープ仕様車は25mm)低くして開閉時にユーザー自身に当たりにくくする工夫が凝らされている。インテリアでは、運転席肩まわりのスペースを+5mm、後席肩まわりのスペースを+55mm、室内有効居住長を+10mmとするなどゆとりをアップさせながら、運転席まわりのデザインも一新。各種小物入れの配置やスペースも見直された。また、標準装備となるHonda SENSINGの進化も見逃せない。 これらに加え「スロープ仕様車」も独自の進化を遂げている。まずは、「4人乗車モード」から「車いす乗車モード」の切り替えが、従来の5アクションから3アクションへ短縮。また、これは以前から装備されていたが、あたらめて便利だと思ったのが「進路補正機能付き電動ウインチ」。これはベルトで車いすを引き上げる際に、斜めから進入しても左右のベルト巻き取り速度が自動で調整され、車いすをまっすぐにスロープに入れることができるもの。スロープ上で車いすを微調整する必要がなく、介助者の負担を軽減してくれる。 スロープや車いす用の専用モーター(2個)を積んだりと、スロープ仕様車は標準車より重くなるが、車いすが跳ねたり沈み込んだりしないように、全体を見てしっかり作り込まれているという。次回試乗するチャンスを見つけ、これらもしっかりご報告したい。 ■価格(消費税非課税) ・N-BOX スロープ 184万4000円〜196万5000円・N-BOX CUSTOM スロープ 206万7000円〜218万8000円 ...
On 2023年11月17日 / By wpmaster文と写真●Believe Japan 2023/3/31(金)配信 介助する側、介助される側、双方の立場になってビリーヴカー(福祉車両)をインプレッション! レポートするのは、介護経験があり自身も福祉車輌取扱士スペシャリスト資格を持つタレント・モータージャーナリスト 竹岡 圭。今回は、ホンダ ステップワゴン スパーダ 車いす仕様車〈2列目乗車タイプ〉をご紹介します。 ホンダ福祉車両:https://www.honda.co.jp/welfare/ ...
On 2023年3月31日 / By wpmaster国民栄誉賞に輝いた車いすテニスの鉄人 Believerとは? 福祉分野を中心に活躍する「明日を信じて今日を前向きに生きる」ひとたち「Believer」を紹介するコーナー。今回は、ホンダ本社ショールームで開催された福祉車両企画展示「Honda ハート Joy for Everyone」のトークショーに出演されたときの国枝慎吾さんを、特別編としてお届けしたい。 文と写真●Believe Japan 協力●ホンダ 9歳のときに脊髄腫瘍を発症。その後、車いすテニスと出会い、並外れた才能と人一倍の努力によって国内外で圧倒的な強さと前人未到の記録を築き上げてきた国枝慎吾氏。同じ年にすべてのメジャーオープンで優勝する年間グランドスラムを5度達成し、パラリンピックで4個の金メダルを獲得。また、シングルスで107連勝という大記録を打ち立てるなど、高い技術と不屈の精神力で、文字どおり世界最強のプレイヤーとして君臨した。そして2023年1月、世界ランキング1位のまま長い競技生活に終止符を打つ。国枝氏は競技にかけてきた自身の思いや、自分を支えてきた言葉、そしてクルマとの関係について語った。この出演の後日、「パラスポーツの社会的認知度の拡大、スポーツの発展に極めて顕著な貢献をし、広く国民に夢や感動を、社会に明るい希望や勇気を与えた」として、国民栄誉賞の授与が決まる。 国枝さんの活躍によって、車いすテニスをはじめパラスポーツの認知度が大きく高まりました。車いすテニスとの出会いはどのようなものでしたか? テニスとの出会いは家の近くにあるテニスクラブで、10歳くらいのときに初めてテニスラケットを握ったときのことは今でも鮮明に覚えています。でもそのときはまさか活躍して皆さんの前でお話をするようなプレイヤーになれるなどとは思いませんでした。僕自身は 小さい時から活動的で、車いすに乗る前はずっと野球をやっていました。また漫画のスラムダンクが大好き。とくに登場人物の三井くんが好きでして(笑)、バスケットボールをしたかったですね。でもテニスが好きな母の勧めで近くのクラブに行くことになりました。民間のクラブでしたが、その当時から車いすテニスをやっていたのには驚きました。当時はテニスはといえば伊達公子選手が活躍されていて、自分にとっては女性のスポーツというイメージがありました。 正直あまり乗り気ではなかったのですが、実際にプレイを目にすると、車いすテニスがこんなに激しい競技だとは思いもしませんでした。そして、そこで車いすの人とも人生で初めて出会いました。テニスをプレイすることもそうですが、何より衝撃だったのは、「車いすに乗ってもこういった運動ができ、またひとりで生活をして、クルマを運転してテニスクラブに通うことだって可能である」というのを目の当たりにしたことです。そこで出会った人たちは、自力で車いすから降りて、それをクルマに乗せて運転し、また下ろして、とすべて自分でされていました。それを見て「車いすでもひとりで生きていけるではないか」と強く思い、大きく励まされました。 今になって思うと、それは自分にとって、テニス以上に大切な学びであったのかもしれません。 長年にわたり、世界のトップで活躍されましたが、ご自身を支えられてきたものとは何だったのでしょうか? 自分は普通の車いすに乗っても、活発に動きまわっていたので、競技用の車いすを初めて使ってもすぐに上手に動けました。しかしラケットの扱いにはなかなか慣れず、 最初はホームランのような球ばかり打っていました。しかし、日々着実に進化していくプレーを自ら感じて、どんどんおもしろくなっていきました。それを日々続けてトップにたどり着くのですが、もはやだれの背中を追いかけることがなくなってからも、「自身がどれだけ上達し進化していけるのか」ということに、現役の最後まで楽しみを見出すことができました。自分自身でモチベーションを高め、努力していきました。それこそがスポーツの素晴らしさであると思います。 プロ選手になることを意識されたのはいつでしたか? 高校生になるとクラブの理事長から「一度、海外に行ってみてはどうか」と言われました。その当時は国内に自分よりも強い人がたくさんいたので、あまり乗り気ではありませんでしたがとにかく行ってみました。... ...
On 2023年3月17日 / By wpmaster文と写真●Believe Japan 2023/3/15(水)配信 2022年5月に登場して人気を集めている6代目ステップワゴン。その改良点の多くは、福祉車両としての使い勝手や快適性に直結するものが多く、ビリーヴカー(福祉車両)としても注目のモデルだ。今回は「車いす仕様車」をチェックして、その実力を探った! 1996年にファミリームーバーとして誕生して初代以来、ステップワゴンは家族みんながくつろげる広々とした室内空間を標榜してきた。6代目となる最新モデルでは、「国内ホンダ車史上最大の室内空間」を掲げている。 福祉車両にも生かされる新型ステップワゴンのレベルアップ 車いす仕様車は、2列目に車いす乗車するタイプ、3列目に乗車するタイプ、2列目と3列目に車いす2台で乗車するタイプの3タイプが設定されているが、このクルマは2列目に乗車するタイプ。新型ステップ ワゴンの福祉車両は全車「スパーダ」をベースにしている。先代モデルから受け継ぐ3列目の分割床下格納シート「マジックシート」とフローリングフロア、電動ウインチに加え、パワーテールゲート(メモリー機能付き)が福祉車両に全車標準装備されているが、 各部さらに改良が加えられている。 ・「安心」と「自由」を表現したというスタイリングは、クルマ全体的に凝縮感、カタマリ感があり、シンプルでスタイリッシュなデザインからは、使いやすさや機能性が感じられる。・「国内ホンダ車 史上最大の室内空間」というキャッチフレーズだが、全席で快適な居住性を誇る。・ 搭載されている1.5L直噴VTECターボエンジンは力強く、車体は走行中の振動が抑えられ静粛性も高められている。車内での会話がより快適になっている。・車両感覚をつかみやすい視界のほか、サイドウインドウの下端を前後水平にし、1列目より2列目、さらに3列目と着座位置を高くするなど、乗り物酔いをしづらくする工夫も施されている。最新の安全運転支援機能も標準装備される。 気軽に出かけたくなる抜群の乗降性 スロープはスロープ脇にあるロックを引っ張って展開する。 スロープにはダンパーが取り付けられていて、ロックを引いてもスロープが急に倒れていたりする事はなく、安心の設計となっている。スロープは力を必要とせずスムーズに伸ばすことができる。 画期的なのは3列目シートの収納。ショルダー部分についたベルトを上に軽く引っ張るだけで、シートは畳み込まれストンと床下に収まる。 思わずあっけにとられてしまう素早さだ。そしてシート裏とスロープのパネルを展開すれば、車いす乗車ができるフラットなフロアができあがる。一般的な福祉車両では3列目シートを窓側に跳ね上げる構造のため、車いすで乗車すると両側面の視界が遮られてしまうが、ステップワゴンでは3列目シートが床下に収納されるので、車いすで3列目に乗車しても車窓からの景色を楽しめる。また、3列目でも車いすの横に乗車することもできる。 続いてウインチをリリースするボタンを押し、車内にあるベルト(2本)を持ってきて車いすに取り付ける。 次にリモコン操作をすると自動で車いすを車内に引き込んでくれる。ウインチの対応重量は120kg、スロープの許容重量は200kgと大柄な車いすユーザと介助する方でも安心して使える設計だ。 車いすの固定もベルトでしっかりと行えて乗り込み動作は簡単だ。... ...
On 2023年3月15日 / By wpmaster文と写真●Believe Japan 2023/3/8(水)配信 東京青山にあるホンダ本社のショールーム「Honda ウエルカムプラザ青山」で2月に開催された福祉車両企画展示「Honda ハート Joy for Everyone」で注目の福祉車両をチェックしてきた! 普段、F1やMotoGPなどホンダが参戦してきたレース車両などが並べられるホールには、ステップワゴンの車いす仕様車やサイドリフトアップシート車、N-BOX車いす仕様車、フィットテックマチックシステムなどの福祉車両が展示され、多くの来場者が訪れていた。また、展示イベントの終了日前日には、現役引退を表明したばかりのプロ車いすテニスプレーヤー国枝慎吾氏のスペシャルトークショーも実施された! ステップ ワゴン 車いす仕様車/サイドリフトアップシート車 2022年5月に登場した6代目ステップワゴンだが、 その改良点は福祉車両としてのクオリティを大いに高めるものばかりだ。 ・「安心」と「自由」を表現したというスタイリングは、クルマ全体的に凝縮感、カタマリ感があり、シンプルなデザインからは使いやすさや機能性が感じられる。 ・「国内Honda車 史上最大の室内空間」というキャッチフレーズの室内は全席で快適な居住性を誇る。 ・車両感覚をつかみやすい視界と乗り物酔いをしづらくする工夫、さらに最新の安全運転支援機能が標準装備される。 新型ステップ ワゴンの福祉車両は「スパーダ」をベースに、車いす仕様車とサイドリフトアップシート車が設定される。先代モデルから受け継ぐ3列目の分割床下格納シート「マジックシート」とフローリングフロア、電動ウインチに加え、パワーテールゲート(メモリー機能付き)が福祉車両に全車標準装備されている。... ...
On 2023年3月8日 / By wpmaster文●Believe Japan 写真●ホンダ 2022/10/24(月)配信 現在乗っているクルマに、ペダル踏み間違い防止機能を後付けできる便利なアイテムがあるのをご存知だろうか。 昨今、免許証の返納が話題ではあるが、高齢ドライバーによる事故は増え続け、その多くがアクセルとブレーキペダルの踏み間違いによる事故だ。新しいモデルには踏み間違いを防止する機能が搭載されているが、できることなら今乗っているクルマを買い替えずに、より安全に運転したいと思われる方も多いだろう。 ホンダ車の純正用品を扱うホンダアクセスが販売している「踏み間違い加速抑制システム」 は、駐車時にブレーキペダルを踏むはずが、間違えてアクセルペダルを踏み込んだ場合に警告しながら加速を抑制する機能。価格は5万2800円(消費税10%抜き4万8000円)。また、別途取り付け費用が必要となる。 高齢ドライバーにとって効果の大きい加速抑制機能 前進時の加速抑制機能 ①フロントに取り付けられたセンサーが前方およそ3メートル以内に障害物を検知すると、時速10km以下で前進した場合で、アクセルペダルを強く踏み込むとランプとブザーで警告する。 ②そのままアクセルペダルを強く踏み続けると加速が自動的に抑制され、ランプとブザーで警告する。加速抑制中はアクセルペダルを踏んでいても、出力がアイドリング状態に抑えられ、加速抑制中にアクセルペダルを約4秒以上強く踏み続けると加速抑制機能は解除され、ゆるやかに加速する。 後進時の加速抑制機能 ①停車状態から「R」レンジのときにアクセルペダルを強く踏み込むと、障害物の有無にかかわらず加速を抑制し、ランプとブザーで警告する。 ②後進時、時速約5kmを超えてアクセルペダルを踏んでいると、加速が抑制されランプとブザーで警告する。 加速抑制中でもアクセルペダルを約4秒以上強く踏み続けると加速抑制機能は解除され、ゆるやかに加速する。 ■取り付け可能モデル ・フィット(年式 2007年10月~2013年8月)※MT車を除く・N-BOX(年式 2011年11月~2017年8月)・N-ONE(年式 2012年11月~2020年3月)※N-ONE Modulo... ...
On 2022年10月24日 / By wpmaster文●Believe Japan 写真●Believe Japan、ホンダ 2022/5/26(木)配信 ホンダが6代目にあたる新型のステップワゴンを5月27日に発売する。新型には、ビリーヴカー(福祉車両)として、「スパーダ」をベースにした「車いす仕様車」と「サイドリフトアップシート車」を設定。価格は339万6000円~383万円(非課税)。 新型ステップワゴンは、「素敵な暮らし」をグランドコンセプトに、乗る人すべての安心と自由への思いに応えるクルマとして作られた。乗り物酔いしにくいように水平基調のベルトラインを室内に通したり、シートの形状を工夫することで2列目、3列目からの視界を広くするなどさまざまなアイデアが込められている。同時開発となった福祉車両でもそのコンセプトは受け継がれているという。 ステップワゴン「車いす仕様車」では、車いすを2列目、3列目、そして2列目および3列目に乗車するようにできるが、どのポジションに乗車しても見晴らしがいいのが自慢。その理由は3列目シートの収納方法にある。ライバル車は3列目シートを窓側に跳ね上げる構造のため、車いすで乗車すると側面の視界が遮られてしまうが、ステップワゴンでは3列目シートを床下に収納するため、車いすで3列目に乗車しても窓がそのまま使えるのだ。また、3列目に車いすで乗車したときにもとなりの席が使えるようにするなど、介助者の利便性も考えられている。 新型では、福祉車両の開発にあたって実際のユーザーから利用実態を調査し、それを反映したという。そのひとつが、リクライニング車いすへの対応。2列目の床に専用の固定点を増設することでこれを実現した(2列目乗車タイプ)。スロープの角度や操作のために必要な力の具合なども利用者の意見を参考している。メモリー機能付きパワーテールゲートを全車標準装備としたのも、利用者に女性が多く、重たいバックドアの開け閉めが不便だという声に答えたからだ。 こうしたユーザー目線の徹底は、機能面だけに止まらない。通常、ミニバンの福祉車両は施設など事業者が購入するケースが多く、そのためコストパフォーマンスのよさが厳しくチェックされるが、ステップワゴンの場合、ユーザーの多くが個人所有のため、求められるニーズが異なってくるのだという。つまり、福祉車両であっても、クルマとしての魅力が同時に求められるのだ。 そこで新型ではベースとなるグレードを上質さをテーマにした「スパーダ」に設定。走行中の死角を補う「ブラインドスポット インフォメーション」や、3列目まで空調を独自に操作できる「トリプルゾーンコントロールフルオートエアコンディショナー」といった充実した装備に加えて、デザイン面でも気を配る。フラットな床はフローリング仕上げで、落ち着いたダーク調の木目柄がシックな雰囲気を演出。バックドアなどのデザインもできるかぎりスタイリッシュなものになるように、ベースモデルの設計段階から参画。プラチナ調クロームメッキでこだわりの外観デザインを引き締めた。その出来栄えに開発スタッフは「乗っている人が誇りに思えるようなカッコいいデザインに仕上がった」と胸を張る。 福祉車両としての機能、利便性に加えて、クルマ本来の魅力を大いに高めた新型ステップワゴンは、福祉車両のある暮らしを明るく、楽しくしてくれる力作だ。 ●価格帯(消費税非課税)車いす仕様車:355万5000円〜383万円サイドリフトアップシート車:339万6000円〜363万6000円 ...
On 2022年5月26日 / By wpmaster文と写真●Believe Japan 2022/4/18(月)配信 介助する側、介助される側、双方の立場になってビリーヴカー(福祉車両)をインプレッション! 今回レポートするのは、自動車ジャーナリスト 石井昌道。足動運転補助装置「Honda・フランツシステム」搭載のフィットをご紹介します。 ...
On 2022年4月18日 / By wpmaster2022/4/8(金)配信 Hondaの中古車サブスクリプションサービス展開エリアが全国へ拡大 Honda は、中古車サブスクリプションサービス「Honda Monthly Owner(ホンダ マンスリー オーナー)」の展開エリアを、2022年4月7日(木)より全国47都道府県、378拠点に拡大すると発表した。 Honda Monthly Ownerは、所有する喜びと利用の気軽さを両立した、国内自動車メーカー唯一の、1カ月単位でHonda車の利用ができるサブスクリプションサービス。2020年1月のサービス開始以降、「これからHonda車に乗ってみたい」というひとに加え、複数所有のお試しや、若年層を中心とした「クルマを保有する生活を体感してみたい」という声などのニーズに対し、「最短1カ月から利用できる」手軽さや、「諸費用込み」という料金体系のわかりやすさについて評価を受け、現在約3900名に会員登録者がいるという。 【Honda Monthly Ownerサービス概要】 税金やメンテナンス費用、自動車保険料などがワンパックで、最短1カ月から最長11カ月まで、定額でHondaの中古車を利用できるサブスクリプションサービス。Hondaの安全運転支援システム「Honda SENSING(ホンダ センシング)」をはじめとした、先進装備を搭載した車両に加え、「車いす仕様車」など充実のラインアップから選ぶことができる。 Honda Monthly OwnerのHPはこちら... ...
On 2022年4月8日 / By wpmaster© 2016-2020 Believe Japan, Inc. All rights reserved.