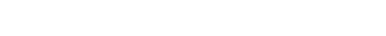文と写真●Believe Japan 2021/7/6(火)配信 2018年、2019年と2年連続でミニバンナンバーワンの販売台数を記録した日産セレナは、2020年8月にマイナーチェンジを受け、ライフケアビークル(福祉車両)シリーズも同時に刷新されている。我々は以前2017年モデルを試乗したが、ファミリー層から多くの支持を得ているベースモデルの総合力はそのままに、福祉車両としての完成度の高さに関心した。今回は、刷新された車いす利用の方のためのスロープ車「チェアキャブ スロープタイプ」をあらためてチェックしてみる。2列目と3列目に1台ずつ車いす乗車ができる「車いす2名仕様」だ。 マイナーチェンジでアナウンスされている改良点としては、ベース車と同様に「インテリジェントFCW(前方衝突予測警報)」が全車標準装備となり、全方位運転支援システムがさらに進化していること。さらに以前はオプション設定だった運転支援技術「プロパイロット」がグレードにより標準装備になり、「インテリジェント ルームミラー」もオプション設定のグレードが拡大されている。加えてUSB電源ソケットが1.0Aから「2.4A」に強化されるなど、安全性や快適性が高められている。 セレナは広々とした室内空間をはじめ、大きく開くスライドドアや高さのあるバックドア、フラットなフロアといったアクセスのよさが大きな魅力となっているモデルだが、それは車いすでアクセスするこの「チェアキャブ スロープタイプ」でさらに際立つ。バックドアから車いすのまま車内に乗り込めるよう、手動式のスロープや車いす乗降アシスト装置(電動ウインチ)、車いす固定装置(電動式)が装備される。 この「車いす2名仕様」は、2列目と3列目にそれぞれ車いす(計2名)で乗車できるタイプ。車いす2名乗車の場合は、同乗者3名の計5名、車いす1名乗車の場合は、同乗者6名の計7名が乗車できる。セレナの美点である広い室内は遺憾なく発揮され、いずれの乗員も快適な移動が可能となる。そしてストレッチャーの乗車(同乗者3名の計4名)にも対応するなど、さまざまなシチュエーションに対応するシートアレンジは秀逸だ。 セレナ「チェアキャブ スロープタイプ」にはほかにも用途にあわせたバリエーションが設定されている。2列目に車いす1名乗車が可能で同乗者6名の計7名乗車が可能な「車いす1名セカンド仕様」、3列目に車いす1名乗車と同乗者5名(e-POWER車は4名)の計6名(e-POWER車は5名)乗車が可能な「車いす1名サード仕様」だ。 乗り降りの機能 車高調整スイッチを押して、後輪の車高を下げる。油圧式のスムーズな動作で、車高が80mm下がり、スロープの傾斜角が大幅に緩やかになる。車いすに座る方にとっても、車いすを押す方にとっても快適で安心感がある。 車いすを固定するフックの取り付けや電動ウインチの操作も非常にわかりやすいのは変わらず。電動ウインチもなめらかに作動し、スムーズな車いす乗車ができる。スイッチ類は室内最後尾の左側にまとめられている。 電動ウインチの操作リモコンは、車いすの手押しハンドルを支えながらでも持ちやすいカタチになっていて、ボタンも少なく大きく、押し間違いを防いでいる。 乗員の乗り降りをラクにしてくれるオートステップ便利なオプションだ。ランプも点灯して暗い場所や夜間での乗り降りもサポートしてくれる。 車内の移動がしやすいフラットなフロア。サイドドアからの3列目へのアクセスも良好だ。車いすスペース用フロアマットの色は、これまでグレーであったが、新しくホワイト系の木目調が選べるようになった。室内の雰囲気が明るくなり、オススメだ。 セレナのライフケアビークルは、スロープタイプのほかに、助手席、または2列目左側シートが、車両の外側に電動で回転・昇降することでアクセスが容易な「助手席スライドアップシート/セカンドスライドアップシート」、リモコン操作で昇降する全自動リフターを装備し、車両後部から車いすのまま車内に乗り込める「チェアキャブ リフタータイプ」、さらに助手席側スライドドアから3列目シートへの乗降性を向上させるなど施設や病院などの送迎時に、利用者がスムーズに乗降ができるよう工夫された「送迎タイプ」の全4タイプがあるので、またの機会に紹介したい。 ドライビング... ...
On 2021年7月6日 / By wpmaster日産自動車とオーテックジャパンは、福岡県北九州市の西日本総合展示場で開催される「第21回 西日本国際福祉機器展」(11月14日から11月16日の3日間)に、福祉車両であるライフケアビークルを4台出展すると発表した。 展示される車両は、8月にマイナーチェンジした新型「セレナ チェアキャブ スロープタイプ」や、100%モータードライブの電動パワートレイン「e-POWER」を搭載した「ノート e-POWER 助手席回転シート」、法人ユースに適した全自動リフター付きの「NV350キャラバン チェアキャブ 車いす1+1名仕様」、大きな車いすも乗せられる軽自動車「 NV100クリッパーリオ チェアキャブ」の計4台。 日産は、「ニッサン インテリジェント モビリティ」の取り組みのもと、クルマの「電動化」、「知能化」に向けた技術開発を進めており、ライフケアビークルにおいても、「ニッサン インテリジェント モビリティ」を具現化する先進技術の搭載を推進している。 展示車両は次のとおり。 ・セレナ チェアキャブ スロープタイプ... ...
On 2019年11月5日 / By wpmaster日産は、ノート e-POWERに4WDを設定すると同時に一部改良を行い、2018年7月5日に発売した。 今回設定された4WDは、e-POWERの走行性能をそのままに、全輪モーター駆動による緻密なコントロールを行うのが特徴。凍結した登り坂や交差点での右左折時、タイヤへの抵抗が大きな深い雪道でも安心した走行が可能となっている。 また、これに併せてノートの仕様変更を実施。具体的には「e-POWER S」を除く全グレードに、アクセルペダルとブレーキペダルの踏み間違いによる衝突防止を支援する「踏み間違い衝突防止アシスト」を標準装備したほか、従来e-POWERの一部グレードに採用していた「インテリジェント クルーズコントロール」と「インテリジェントLI(車線逸脱防止支援システム)」が、ガソリン車にも拡大採用されることになった。 ノートには「助手席回転シート(e-POWERの設定あり)」と「助手席スライドアップシート(e-POWERの設定なし)」の2タイプの福祉車両があるが、これらにもベース車と同様の仕様変更が適用されている。 ●価格帯 ノート 助手席回転シート:163万1880円~268万8120円 ノート 助手席スライドアップシート:183万6000円~206万1000円 ※「助手席スライドアップシート」は消費税非課税。 ...
On 2018年7月5日 / By wpmaster文と写真●Believe Japan 高齢者や障がいのある方の快適な生活を提案する総合福祉展「バリアフリー2018」が、4月に大阪で開催された。今年も開催3日間で、延べ8万8260人が来場する大きな盛り上がりを見せ、自動車メーカーのブースには、最新の福祉車両を見るため、来場者が詰めかけていた。 ここでは、注目を集めていた福祉車両を紹介していく。まずはミニバンの人気モデル日産「セレナ」から生まれたコンセプトモデル「アドベンチャーログキャビン(Adventure Log Cabin)」。福祉車両をはじめ、日産の特装車を手がけるオーテックジャパンによるこのモデルは、多くの来場者に衝撃を与えるものとなった。モーターショーでは、近未来的なフォルムや斬新な機能をうたったコンセプトモデルがメーカーから発表されることが多いが、福祉車両としては非常に珍しい。 遊び心あふれるスタイリング 「アドベンチャーログキャビン」は、福祉車両「セレナ チェアキャブ スロープタイプ」をベースとしたコンセプトカー。ボンネットからルーフにかけてブラックに装飾したボディラッピングに加え、「冒険」をイメージさせるルーフキャリア、オフロードタイヤの装着など、アクティブかつワイルドなルックスで、アウトドアの雰囲気を明るく演出している。 バリアフリー展の直前に開催された子どもの福祉用具展「キッズフェスタ 2018」にも展示され、好評だったというアドベンチャーログキャビン。ベースのチェアキャブ スロープタイプは、「車いすに乗る子ども」の快適さを第一に考えたレイアウトであったが、このコンセプトモデルでは、さらに「一緒に出かけることをもっと楽しむ」というメッセージが込められているようだ。車いすスペースにベージュ系の内装色に調和する、明るい木目調のフロアマットが装着されている。「明るい子供部屋」をイメージしたということで、見た目だけでなく、乗る人の気持ちも明るくなるように考えられている。 ドライバーから近い距離に座れるよう、車いすのポジションは、前に、そして中央寄りになっている。スライドドアからは、車いすの後ろを通って、3列目にアクセスできる。 スウェーデンのカーキャリアブランド「THULE(スーリー)」のルーフキャリアを装着する。マットブラックのカラーが絶妙なアクセントとなっている。 ... ...
On 2018年5月16日 / By wpmaster日産は、eパワーシステムを搭載した「セレナ eパワー」を発表し、2018年3月1日から発売する。同時にセレナの福祉車両「ステップタイプ」、「セカンドスライドアップシート」、「チェアキャブ スロープタイプ」にもeパワー仕様が設定された。 セレナ eパワーは、発電用エンジンを搭載し、その電力を利用してモーターで走行するタイプの自動車。コンパクトカーのノートに初搭載され、今回はトールサイズミニバンのセレナにも設定されることになった。 eパワーは100%モーターで駆動するため、クラスを超えた高い静粛性が特徴で、さらにボディ各部に防音対策を施すことで快適な室内空間を実現している。また、今回はバッテリーだけで走行可能な「マナーモード」を新設定。さらにこの「マナーモード」を活用するべく、事前にバッテリーに充電しておく「チャージモード」も用意され、夜間の帰宅や外出でも騒音を気にすることなく安心して乗ることが可能となった。 デザイン面では、フロントグリルをはじめ、エクステリアおよびインテリアにブルーアクセントが施されるのが特徴。標準仕様のセレナと同じく、高速道路の同一車線においてアクセル、ブレーキ、ステアリングを自動で制御する「プロパイロット」も採用する(一部グレードにオプション装備)。 ●価格 セレナ ステップタイプ eパワー:338万6880円〜366万2280円 セレナ セカンドスライドアップシート eパワー:343万9000円〜369万4000円 セレナ チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名サード仕様 eパワー:353万1000円〜372万5000円... ...
On 2018年2月28日 / By wpmaster日産は、ドライバーの脳波を測定し、運転支援を行うという研究を発表した。 この技術は「B2V(Brain-to-Vehicle)」と呼ばれ、ドライバーがヘッドセットを着用することで脳波を検知し、ドライバーのイメージどおりにクルマを動かせるシステムである。 具体的には、ハンドルを回すなどの運転操作に関連する行動準備電位のリアルタイムな検出、さらにドライバーが頭のなかでイメージする運転と実際の運転が違うと感じるときのエラー関連電位の計測が、世界で初めて可能になった。これにより、ドライバーの反応の遅れをクルマがカバーしてくれたり、自動運転モードの際、違和感のない走りを実現できるようになるという。 この研究に対し、日産の副社長であるダニエレ・スキラッチ氏は、「将来の自動運転社会では、人間はクルマをコントロールしないと考える人が多いかもしれません。しかし、この技術はその反対です。ドライバーの脳波を活用して、ドライビングをさらにエキサイティングで楽しいものにしていくのです」と述べている。 また、B2V技術の研究をリードしている同社のルチアン・ギョルゲ氏は、「この技術の適用には大きな可能性があります。この研究が触媒となり、将来、より多くのイノベーションが日産車にもたらされるでしょう」と述べており、今後の自動運転化社会の到来をさらに後押しするものになりそうだ。 なお、同社は今回発表した技術を、ラスベガスで開催される「CES 2018」に出展し、ドライビング・シュミレーターを用いてB2V技術のデモンストレーションを行う予定となっている。 ...
On 2018年1月5日 / By wpmaster2017年の2月末にセレナのライフケアビークル(福祉車両)シリーズにチェアキャブ(車いす仕様)「スロープタイプ」が新たに設定された。今回われわれは、実際に車いすで乗り降りの使い勝手や市街地走行、高速走行を織り交ぜての長距離移動を試し、そのポテンシャルを探ってみることにした。 関連記事:【日産セレナ チェアキャブ スロープタイプ 2017】を試乗でチェック English subtitled movie (英語字幕付き動画) ...
On 2017年7月4日 / By wpmaster文●Believe Japan 写真●Believe Japan、日産自動車 ファミリー層から絶大な人気を誇る日産のミニバン「セレナ」が、2016年の8月にフルモデルチェンジを行い、さまざまな新機能を搭載して話題を呼んでいる。 そして、ライフケアビークル(福祉車両)シリーズにチェアキャブ(車いす仕様車)「スロープタイプ」が新たに設定されたのが2017年の2月末。今回我々は、実際の使い勝手に加え、市街地走行と高速走行を織り交ぜた長距離移動を試し、そのポテンシャルを探ってみることにした。 チェックしたのは「セレナ チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名セカンド仕様」。2列目に車いすで乗車するタイプだ。新型セレナは運転席から3列目まで、すべてのひとが楽しく快適に移動できることを目標に開発されたという。標準車の資質は、福祉車両にもダイレクトに反映されるから楽しみだ。ちなみにスロープタイプには、そのほか「車いす1名サード仕様(3列目)」、「車いす2名仕様(2、3列目)」、そして専用シートレイアウトや手すり、オートステップを装備した施設送迎向けの「車いす1名送迎仕様(3列目)」の計4タイプが設定されている。 【使い勝手】 まず、車いすで乗り込んでみて、実際の使い勝手を確かめてみた。後輪が油圧式車高調整機構になっていて、ワンタッチで速やかに車高を下げ、スロープの傾斜をゆるやかにすることができる。油圧の車高調整と電動ウインチはなめらかに作動し、車いす固定フックの取り付けや電動ウインチの操作も非常にシンプル。おかげでスムーズな車いす乗車ができた。 開発生産を担当しているのは、日産の関連企業で特装車を手がける「オーテックジャパン」。これまでさまざまなスポーツモデルやカスタムモデルなどを手がけ、その開発力とエンジニアリングで高く評価されているメーカーである。 車いすの乗り降りに関する操作系は、リヤゲートを開けた左側にまとめて配置されている。車高調整のスイッチ(写真右上)、電動ウインチベルトの引き出しや固定、解除のスイッチ(写真右下)は、簡単に操作できる。また、電動ウインチの操作リモコン(写真左)は、介助するひとが車いすの手押しハンドルを支えながらでも持ちやすい形状になっている。ボタンを大きく、また数も少なくすることで押し間違いを防止している。 3列目シートの頭上にあたる部分の天井部は、中央部分が上方向にくぼんでいる。これは、乗り降り時に頭をぶつかりにくくする配慮である。... ...
On 2017年7月4日 / By wpmaster文と写真●Believe Japan 高齢者や障がいのある方の快適な生活を提案する総合福祉展「バリアフリー2017」が、今年もインテックス大阪で開催された。23回目を迎えるバリアフリー展は、もはや春の風物詩としてすっかり定着し、今年は4月20日(木)~22日(土)の3日間で、のべ9万1356人という多くのひとが来場した。 医療、福祉にまつわるさまざまなデモンストレーションや展示、講演会などが行われたが、やはり福祉車両に対する注目度は高く、自動車メーカーのブースには、連日多くの来場者が訪れて、スタッフに対して熱心に、展示車両の機能や使い勝手などを確認している姿が見られた。各メーカーも注目のニューモデルを大々的に展示し、新しい機能などを積極にアピールした。 最近では、福祉車両を展示して、乗り降りなど実際の使い勝手を試すことができるショールームが増えている。それらは、バリアフリーはもちろん、それぞれの車両のまわりには大きなスペースがあるため、車いすでも自由に移動できるのでとても快適だ。しかし、福祉車両が数多く一堂に会して展示されるという機会は稀で、メーカーの垣根を越えて、気になるモデルを自由に比較できるということは、多くのユーザーにとってもありがたい。 ここでは、とくに関心の高かったモデルをメーカーごとにピックアップして紹介したい。 【トヨタ】 福祉車両をリードするトヨタのブースでは、コンパクトからミニバンまで、多様なラインアップで、終日賑わいを見せていた。そのなかで目立っていたのが、ハイブリッドモデルの人気の高さだった。会場では、福祉車両の燃費の目安について質問する来場者の姿も多く、その熱気の中心にあったのがプリウスPHEVの助手席回転チルトシート車。標準車の注目度の高さは福祉車両でも変わらず、実際に乗り降りを体験するための列ができるほどの人気ぶりだった。 プリウスPHEV 助手席回転チルトシート車 チルトシートは乗り降りされる方の腰の位置が高いことから、立ち上がりやすく、着座時も膝の角度がゆるやかで負担が少ないのが特徴。また、手動式のためスピーディーな操作が可能という手軽さもアピールしていた。 アーティスト大峰直幸氏によるデザインラッピングが施されたシエンタ。トヨタではおよそ30年前から、障害のあるひとの芸術活動を支援している。 【ホンダ】 8台の福祉車両が展示されたホンダのブースでは、「いつでも、どこでも、だれでも用途に応じて思いどおりに使える」というキャッチフレーズの新型コンパクトミニバン「FREED(フリード)」とホンダの福祉車両として高い人気を誇る「N-BOX」が主役だった。コンパクトながらも広大な室内空間を活かし、車いす利用者も含めて最大6名の乗車を可能とした「FREED+(フリード... ...
On 2017年5月5日 / By wpmaster日産のミニバン「セレナ」のライフケアビークル(LV)シリーズに 、新たにチェアキャブ「スロープタイプ」が設定された。 今回登場する「スロープタイプ」は、セレナの持つ室内の広さや使い勝手の良さを生かし、バックドアから車いすのまま車内に乗り込めるよう、手動式のスロープと車いす固定装置を装備している。全4仕様のラインアップとなり、車いす1名を含む7名乗車や車いす2名を含む5名乗車など、高いユーティリティが注目を集める。 車いす1名 セカンド仕様 車いすは2列目左側に乗車し、右側には介助者などが並んで座れる。車いす1名を含めて7名の乗車が可能。 車いす2名仕様 2列目左側と格納した3列目シートの位置に、同時に2名が車いす乗車することができる。車いす2名を含めて5名の乗車が可能。 車いす1名 サード仕様 車いすは3列目シートの左右を格納して乗車し、車いす1名を含めて5名の乗車可能。車いすの方が乗車しない場合は定員7名乗車となる。 車いす1名 送迎仕様 高齢者の乗降に配慮した乗降用手すりやオートステップが備えられ、さらにセカンドシートを専用形状の2人掛けとするなど、3列目シートへのアクセスを容易にした仕様。福祉施設の送迎にも適している。 全仕様とも、車いすの乗車位置を車両の前方に、そして中央寄りにすることで、運転席の近くに車いす乗車できるようになっていて、安心感が高い。また、車いすのスペースは、大きな車いすにも対応できるゆとりが確保されている。さらに、2列目の車いす乗車の位置の横にフルフラットリクライニングできるシートを装備し、停車中はフルフラットにして車いすの使用者をケアすることなども可能となる。 日産では、このスロープタイプのセレナは、家庭はもちろん、福祉施設や病院、福祉タクシーなどの幅広いニーズに対応できると考えている。 【価格帯】 セレナ... ...
On 2017年2月7日 / By wpmaster© 2016-2020 Believe Japan, Inc. All rights reserved.