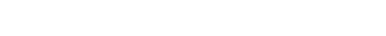文●Believe Japan 写真●ホンダ 2021/3/9(火)配信 今日、「家族に高齢者がいる」、「乗り降りがしんどい」など、アクセスが便利なクルマを必要としている潜在的なユーザーは少なくない。それに応えるビリーヴカー(福祉車両)は、設定車種が大幅に拡大され、趣味やライフスタイルに合った車種選びも可能になってきている。しかし、買い替えコストや「自身で歩くことができる」などの状況によって、ビリーヴカーを購入するまでに至らないケースもあるだろう。多くの場合は、できれば後付けのパーツで、手軽にクルマを便利で安心なものにしたいと考えているのではないだろうか。 アクセサリーといえば、エアロやアルミホイール、LEDランプなどドレスアップ方向のパーツをイメージしがちだが、じつは高齢者にやさしいパーツがたくさんあるのをご存知だろうか? これらのパーツは、高齢の家族と暮らしていればもちろん、そうではなくても、広く一般的に使えるアクセサリーであったりする。手軽なカスタムを可能にするアクセサリーには数々の製品がラインアップされている。今回はその中から、ホンダ車に注目。実際にどのようなアクセサリーがあるのか見てみたいと思う。 幅広い年代のファミリー層から高い人気を集める「N-BOX」や「フリード」、「ステップワゴン」、そして「オデッセイ」には高齢者ユーザーのクルマ移動を快適にしてくれるアクセサリーが豊富に用意されている。 つかめる安心感 足もとに不安があると、どこかにつかまる必要がある。ビリーヴカーでは、一般車にはない場所にさまざまなグリップが取り付けられている。あらゆるタイプがあるが、ここでは代表的なものを一部紹介する。 [シートバックグリップ(N-BOX、フリード、ステップワゴン )] 横に広くつかみやすいタイプの乗降用「シートバックグリップ」は、乗り降り時と車内での移動に便利だ。アクセスを簡単で安全にしてくれる。価格は1万780円(税込み)。 [フロアグリップ(フリード、ステップワゴン)] 助手席の座面横に取り付けられた「フロアグリップ」は、しっかりとつかむことができ、クルマの乗降時に加え、走行中の姿勢安定にも効果を発揮する。多くの人にとって便利な優れものである。本体とグリップパッドの合計価格は2万6950円(税込み)。 [吊革グリップ(N-BOX、フリード、ステップワゴン、オデッセイ )] 山道を走行する時など、後席に座る人は上半身を前に乗り出し、サイドウインドウの上に取り付けられたグリップをつかんでいることが多い。ところが、体格や年齢などによっては、腕を上げている姿勢はかなりの負担になることもある。そこで、通常のグリップを「吊革(つりかわ)」タイプにしてしまうアクセサリーが「吊革グリップ」だ。腕を高く上げる必要がなく、ラクな姿勢でしっかりと握ることができる。使用しないときは巻き上げ可能で、視界の邪魔にならない。価格は5280円(税込み)。 [ドリンクホルダーグリップ(フリード、ステップワゴン)] ダッシュボードのドア側に設置されたドリンクホルダーは、丁度よい取手としてつかみながら車内に乗り込む場合もあるが、これをつかみやすい「グリップ」にしてしまうアクセサリーがある。腕を上げなくても手がかけられる高さにある「ドリンクホルダーグリップ」は、価格は9350円(税込み)。 みんなに優しい装備 高齢者や歩行困難な方だけでなく、多くの人にとっても「あれば便利」なアクセサリーもある。 [テールゲートストラップ(N-BOX、フリード、ステップワゴン、オデッセイ )] 車高が高めのクルマの場合、リヤゲートを開けるのは問題ないが、閉めるときにドアが届かないという場合がある。つかみやすく、ラクに閉められる「テールゲートストラップ」は背が届かない、腕を上げにくいといったユーザーにとって優しいアクセサリーだ。価格は1100円(税込み)。... ...
On 2021年3月9日 / By wpmaster文と写真●Believe Japan 2021/2/12(金)配信 ホンダの上級ミニバン「オデッセイ」が、昨年末に大幅マイナーチェンジを実施。それにともない、車いす利用の方や足腰の弱い高齢の方に便利な「サイドリフトアップシート車」と「助手席リフトアップシート車」も新しくなった。 新型オデッセイが目指したのは、『さらなる上質さと心地よさの向上』。厚みのあるフロントマスクの採用で外観はグッと迫力を増したが、むしろ注目すべきは、既存ユーザーから徹底的にヒアリングを行い見直したという、その中身だろう。 たとえば、インテリアではインパネまわりが全面的に変更され、ナビゲーションパネルの大型化(10インチ)やコンビメーターの形状変更、手の触れやすい位置へのソフトパッドの配置、収納式ドリンクホルダーの追加、インパネアッパーボックスをリッド付きにするなど、ユーザー目線で変更されている。 また、静粛性を高めるべくフロントドアガラス/スライドドアガラスの遮音化、テールゲートガラスの板厚アップに加え、ノイズリデューシングホイールも採用するという徹底ぶり。安全運転支援システム「ホンダセンシング」では、後方誤発進抑制機能が新たに加わった。 オデッセイの回転シート車には、「サイドリフトアップシート車」と「助手席リフトアップシート車」があるが、これは車いす利用の方(もしくは足腰の弱い高齢の方)がどちらに座って移動したいかで決まることが多いという。つまり、家族内で相談しましょうというわけだ。ユーザー目線で言えば、選べるところがありがたい。 今回試乗したのは、新たにアブソルートに設定され、2.4Lガソリンエンジンを搭載した「サイドリフトアップシート車」。市街地、高速道に加え、ちょっとした山道でも試したが、全行程でドライバー、2列目シートとも落ち着いて乗れる1台に仕上がっていた。この「落ち着いて乗れる」ことは、通常のクルマに加えてビリーヴカー(福祉車両)にとっても非常に重要なチェック項目。リラックスできる環境であれば、おのずと笑顔も増えるもの。 現在、この車格で選べるビリーヴカーはさすがに少ない。快適性の話はベースとなるクルマそのものに起因する話ではあるが、今回改めて、車いす利用の方や足腰の弱い高齢の方に、オデッセイはやさしいクルマだと感じた。 ホンダ オデッセイ アブソルート サイドリフトアップシート車 FF/7人乗り(CVT) ■全長×全幅×全高:4855×1820×1695mm■ホイールベース:2900mm■トレッド前/後:1560/1560mm■車両重量:1830kg■エンジン:直4DOHC■排気量:2356cc■最高出力:175ps/6200rpm■最大トルク:23.0kgm/4000rpm■サスペンション前/後:マクファーソン式/車軸式■ブレーキ前/後:Vディスク/ディスク■タイヤ前/後:215/60R17 ■車両価格:363万4000円(消費税非課税) 関連リンク:ホンダ福祉車両(https://www.honda.co.jp/welfare/) ...
On 2021年2月12日 / By wpmaster文と写真●Believe Japan 2021/2/9(火)配信 先日デビューした「マツダMX-30 EV MODEL」は、マツダの新しい歴史を刻む1台。フリースタイルドア(観音開きドア)を採用した独創的なスタイリングとEVならではのスムーズな走りのコンビネーションは、「クルマってまだまだ楽しいな」と素直に思わせてくれる。そして、驚いたことにこのクルマには、新しい福祉車両がスタンバイしている。 正式なデビューはこの秋ということで、触れることができたのは試作段階の車両だが、その印象をお伝えできればと思う。 じつはマツダの福祉車両の歴史は古く、59年前に市販された「R360クーペ」の手動運転装置付車が最初の1台となる。以降、スロープ式車いす移動車などを手がけ、現行モデルでは手動運転装置付車「ロードスター/ロードスターRF」、助手席回転シート車「マツダ2」、リフトアップシート車「CX-5」、車いす移動車「フレアワゴン」がラインアップされている。 今回の「マツダMX-30 EV MODEL」の福祉車両は、福祉車両という枠組みではないモデルとして成長させたいとの思いから、「Self-empowerment Driving Vehicle」との名称が与えられた。大きな特徴と言えるのは、アクセルにリング式を採用していること。日本では、これまで自操式車両というとAPレバー式(左手でアクセル/ブレーキ、右手でステアリング)が定番だったが、リング式(左手でブレーキ、両手でアクセル)だと両手でハンドルを握ることができ、自然な姿勢で運転できることはもちろん、運転中にドリンクを飲むこともできる。 欧米ではわりとスタンダードなリング式。これまで日本でもパーツを海外から取り寄せ、専門的なショップで自車に取り付けるといったことは行われていたが、自動車メーカーのラインアップとして登場するのは初めてのこと。ちなみに、このモデルはすべてマツダ内製とのことだから、いかに力を入れて開発しているのかがわかる。 また、見逃せないのが世界初という運転切替機能。たとえば家族とのドライブで、行きは身体の不自由な方、帰りは健常者の家族といったように、簡単に切り替えることができるのだ。 敷地内を少しだけ走らせてもらうと、アクセル/ブレーキ操作に関しては、すぐに慣れてしまうほど運転しやすいことがわかった。この馴染みやすさは、あきらかに両手でステアリングを握ることができるから。ブレーキが必要なタイミングでは、スッと左手をレバーに添えればいい。車庫入れのシーンなどで車両をバックさせる際は、レバーでブレーキを固定させ、シフトチェンジしてからブレーキを解除するという手順のため、少しだけ慣れが必要かもしれないが、難易度は高くない。 マツダでは、今回EVモデルにこの「Self-empowerment Driving Vehicle」を設定した理由を、「スムーズな走り」と「自宅で充電できる手軽さ」を強調する。たしかに、セルフがメインとなったガソリンスタンドで、車いすでの給油作業はかなり面倒だ。気になる価格も企業努力の真っ最中とのことだから、楽しみに秋の正式発表を待ちたい。 ... ...
On 2021年2月9日 / By wpmaster文と写真●Believe Japan 2020/9/11(金)配信 介助する側、介助される側、双方の立場になってビリーヴカー(福祉車両)をインプレッション! レポートするのは、介護経験があり自身も福祉車輌取扱士スペシャリスト資格を持つタレント・モータージャーナリスト 竹岡 圭。今回は、手動運転補助装置「Honda・テックマチックシステム」搭載の新型フィットをご紹介します。 ホンダ福祉車両:https://www.honda.co.jp/welfare/ ...
On 2020年9月11日 / By wpmaster文と写真●Believe Japan 2020/9/10(木)配信 「~移動の喜びを一人ひとりに~」。ホンダはこの人間尊重の基本理念のもと、長年クルマを製造・販売しているが、福祉車両(ビリーヴカー)に関しても、その歴史はじつに長い。 現在、福祉車両には大きく分けて「介護車両(介護する側が運転する)」と「自操車両(補助装置を使って自身で運転する)」の2種類が存在するが、ホンダは後者の「自操車両」を、なんと1976年に誕生させていたのだ! 初代シビックに搭載されたのは、両下肢に障がいを持った方へ対応する手動運転補助装置で、「Honda・テックマチックシステム」と呼ばれるもの。その後、ホンダは両上肢に障がいを持った方へ対応する足動運転補助装置「Honda・フランツシステム」も1982年に完成させている。とくに足動運転補助装置は技術的にもハードルが高く、当時の営業スタッフが障がいを持つ一人の女性との出会いがきっかけとなり開発されたというが、その完成までの道のりは長く、まさしくチャレンジの連続だったという。 今回は、手動運転補助装置の「Honda・テックマチックシステム」をクローズアップ。新型フィット用に開発された「Honda・テックマチックシステム」は、e:HEV(イーエイチエーブイ)とガソリン車双方に装着でき、両足が不自由な方向けの「手動運転補助装置〔Dタイプ〕」、右足が不自由な方向けの「左足用アクセルペダル〔Bタイプ〕」、片手が不自由な方向けの「ハンドル旋回ノブ〔Aタイプ〕」、「左手用ウインカーレバー〔Lタイプ〕」がラインアップされている。 ちなみにこの手動運転補助装置。日本ではあまり見かけない印象があるが、欧州ではもっともポピュラーなビリーヴカーといえ、現地の福祉関連イベントの駐車場ではかなりの台数を見かける。地理的な問題はもちろんだが、できるだけひとの手を借りず、自立した毎日を過ごしたいという彼らの生活に根ざした必需品というわけだ。 話は戻って、撮影車は「手動運転補助装置〔Dタイプ〕」に「ハンドル旋回ノブ〔Aタイプ〕」が装着された仕様。運転補助装置と聞くと、なにやら複雑な機構がインテリアの雰囲気をガラリと変えそうなイメージあるが、写真を見てわかるように、じつにすっきりとキレイにまとまっている。とくに足元スペースは広く開放感にあふれていて、コントロールグリップの質感や剛性感も、後付け感がない。この違和感のなさに、長年積み重ねられたノウハウが感じられる。 早速試乗してみると、発進、停止、そしてステアリングのしっとりとしたフィーリングなど、新型フィットの魅力がまったく損なわれていないことを確認。動画レポートを担当した竹岡圭氏も、「思っていた以上に走りが楽しい!」を連呼していた (こちらはインプレッション動画をご覧ください)。 開発メンバーに話を伺うと、「基本的な機能や操作のロジック、耐久性などは自動車メーカーの名に恥じぬものに。また、実際には使用される方の状態にあわせた、いろいろな対応を行っています」とのこと。いまホンダには、実際に福祉車両を見て、試すことができるバリアフリーのお店「オレンジディーラー」があるのをご存知だろうか? ここでは介助士資格取得スタッフが常駐し、いろいろな相談ができるという(介護車両の展示はあり。今回のような自操車両は要相談)。そして、そのような心強いお店が全国に406拠店! もあるというから驚きだ。 車いす生活での移動の重要性は、あらためて語るまでもないだろう。モータースポーツでの活躍や航空業界への進出など、さまざまな分野で実績を積み続けるホンダだが、福祉車両(ビリーヴカー)も諦めないところに、そのチャレンジングスピリットを感じる取材となった。 新型FIT「Honda・テックマチックシステム」Dタイプ。外観は通常モデルとまったく同じだ。 開放感ある運転席まわり。フィットは2本スポークステアリングで、視覚的にもゆとりが感じられる。 このコントロールグリップで、アクセルとブレーキの操作を行う。とても剛性感が高くしっかりしたつくりで、ほかにもハザードスイッチ、ウインカースイッチ、ライトスイッチ(HI/LO)、ホーンスイッチが集約されている。また、〔Dタイプ〕は障がいのない方も運転できるように、コントロールグリップ固定する(機能を停止する)ねじ穴も装着されている。 ハンドル旋回ノブは、「ホーンなし」と「ホーン付き」が選べる。 撮影車には未装着だが、サポートアイテムとして、運転中にアクセルペダルやブレーキペダルを誤って踏むのを防止する「ペダル誤操作防止プレート(Dタイプ用)や、左足のみでアクセルとブレーキの操作が行える「左足用アクセルペダル〔Bタイプ〕」も用意されている。 シートは標準モデルとまったく同じだ。... ...
On 2020年9月10日 / By wpmaster文と写真●Believe Japan 2020/5/22(金)配信 これまで海外では欧州、北米を取材してきた編集部だが、世界の福祉車両を見渡すと、いかに日本の福祉車両が充実しているかがわかる。このサイトの福祉車両検索でも新車ラインアップが探せるが、車種だけでも50種類以上。車種毎の異なる仕様も数えると、その数は約90種類にもおよぶ。もっとも、だからといって海外では福祉車両が消極的というわけではない。欧州も北米も所有しているクルマをカスタムメイドするという市場背景があるからだ。 しかし、これほど充実している日本の福祉車両ではあるが、重量のある電動車いすに対応する車種となると、残念ながらその数は非常にかぎられてしまうのが現状だ。 今回クローズアップするのは、そんな重量級の車いすもスマートに載せられる、新型ロンドンタクシー TX。 ロンドンタクシーといえば、1908年~という長い歴史を持つシックなブラックキャブで、来訪者に成熟した大人の英国を視覚で伝えてくる英国名物。 現在は、ボルボなども傘下に収めるGeelyホールディングスのLEVC(ロンドン EV カンパニー)となっており、そのLEVC社が新たに製造したのが、この「ロンドンタクシー TX」となる。このモデルの最大の特徴は、レンジエクステンダー付きEVであること。発電用の1.5Lのボルボ製3気筒エンジンがリチウムイオン電池に充電(急速充電にも対応)し後輪を駆動する。 導入のきっかけには、どういう背景があったのだろうか。自身も車いす生活の経験があるという、LEVCジャパン 経営企画室長の渋谷剛史さんに伺った。 「車いす生活のなかで痛感したのは、とにかくちょっとした移動が大変なこと。いまでこそ各地でバリアフリー化の声が高まり、事実進んではいますが、それでもまったく足りていないのが現状でしょう。となると、やはりクルマでの移動は必須。ところが、日本では最低限の移動はできても、心が満たされるようなクルマは見当たらない。私自身30年以上自動車販売に携わってきたのですが、この新型ロンドンタクシーTXなら、車いすでも気持ちよく移動ができ、利用するひとたちにも多くのメリットがあると確信しました」 ロンドンタクシーは、先代モデルでもユニバーサルデザインが採用されていて、新型のTXではそれらが進化している。彼らが考えるユニバーサルデザインのポイントは以下のとおりだ。 ●大きな開口部のドアと、ユニークな収納ステップ(操作が簡単) ●フロア下に格納された機能的な車いすスロープ(耐荷重250kg) ●移動しやすいフラットな床面(車内で車いすの回転可) ●聴覚障がい・視覚障がいの方にも配慮した室内空間(色や手すり等)... ...
On 2020年5月22日 / By wpmaster通常モデルに加え、福祉車両(ウェルキャブ)も充実したラインアップを誇るハイエースに一部改良が施された。 今回の改良では、車両後方のカメラ映像を映し出すデジタルインナーミラー(全車にオプション)と車両を上から見たような映像をナビゲーション画面へ表示するパノラミックビューモニター(AT車のみにオプション)を採用し、周囲の安全確認をサポート。また、オプティトロンメーターに4.2インチTFT(薄型トランジスタ)カラーのマルチインフォメーションディスプレイを採用するなど、視認性を向上している。さらに、アクセルペダル踏み間違い時の衝突被害軽減に寄与するインテリジェントクリアランスソナー(Toyota Safety Sense装着のAT車にオプション)を採用するなどし、安全装備の充実が図られている。 ●価格帯 車いす仕様車:368万7000円〜480万円 ウェルジョイン:307万8000円〜417万5000円 ※消費税は非課税(ウェルジョインは消費税込み)。 ※北海道、沖縄のみ価格が異なる。 ...
On 2020年4月17日 / By wpmaster文と写真●Believe Japan 介助する側、介助される側、双方の立場になってビリーヴカー(福祉車両)をインプレッション! レポートするのは、介護経験があり自身も福祉車輌取扱士スペシャリスト資格を持つタレント・モータージャーナリスト 竹岡 圭。トヨタの福祉車両開発担当 中川茂さんをゲストにお迎えし、トヨタ ウェルキャブについて紹介します。特集その⑦は「シエンタ 車いす仕様車&ウェルチェア」について。 トヨタ ウェルキャブ公式サイト:https://toyota.jp/welcab/index.html ...
On 2020年3月10日 / By wpmaster文と写真●Believe Japan 介助する側、介助される側、双方の立場になってビリーヴカー(福祉車両)をインプレッション! レポートするのは、介護経験があり自身も福祉車輌取扱士スペシャリスト資格を持つタレント・モータージャーナリスト 竹岡 圭。トヨタの福祉車両開発担当 中川茂さんをゲストにお迎えし、トヨタ ウェルキャブについて紹介します。特集その⑥は「特別対談:中川氏に聞くこれからの福祉車両」について。 トヨタ ウェルキャブ公式サイト:https://toyota.jp/welcab/index.html ...
On 2020年3月6日 / By wpmaster文と写真●Believe Japan 介助する側、介助される側、双方の立場になってビリーヴカー(福祉車両)をインプレッション! レポートするのは、介護経験があり自身も福祉車輌取扱士スペシャリスト資格を持つタレント・モータージャーナリスト 竹岡 圭。トヨタの福祉車両開発担当 中川茂さんをゲストにお迎えし、トヨタ ウェルキャブについて紹介します。特集その⑤は「ヴォクシー ウェルジョイン」について。 トヨタ ウェルキャブ公式サイト:https://toyota.jp/welcab/index.html ...
On 2020年3月3日 / By wpmaster© 2016-2020 Believe Japan, Inc. All rights reserved.