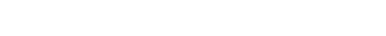文と写真⚫︎Believe Japan 2023/10/13(金)配信 H.C.R. 2023のマツダ ブースに置かれていたのが、3台のSeDV。「SeDV」とは「Self-empowerment Driving Vehicle」の略で、自分の意志で行動、移動し、イキイキと人生を楽しむというコンセプトで生まれた。これらのモデルに共通なのが、手動運転モードと通常運転モードを切り替えられる機能。これにより、下肢障がいを持つひとでも、クルマを自分で運転できるのが最大の特徴となっている。 ブースにはロードスター、CX-30、MX-30のSeDVが展示されていたが、今回初めてお披露目されたのがCX-30 SeDV(参考出品車)である。すでに販売されているMX-30 SeDVと同じく、アクセル操作はハンドルに沿って置かれるアクセルリングで行う。押し込むと加速、離すとアクセルオフという仕組みだ。ブレーキ操作はステアリングの左側にあるレバーで行う。CX-30 SeDVでは左肘を固定するブレーキサポートボードが置かれ、安定したブレーキ操作ができるのも大きな特徴。さらに運転席の右側には移乗ボードが配置され、車いすから乗り込みやすい工夫がなされている。 すでに販売中のMX-30 SeDVと同じく、足踏みのブレーキペダルを踏みながらエンジンを掛けると、通常運転モードとして使える。障がいを持つひとが、家族や友人と運転を交代しながらドライブに行けるのは非常に魅力的。発売は2024年とのことだが、福祉車両にまたひとつ便利なモデルが加わることになりそうだ。 ...
On 2023年10月13日 / By wpmaster文と写真⚫︎Believe Japan 2023/8/24(木)配信 新しく生まれ変わった日産セレナ。そのビリーヴカー(福祉車両)に、ようやく試乗するチャンスがやってきた。 先代モデルも、その扱いやすさや高い機能性、スタイリッシュさで人気のモデルだったが、新型セレナはその魅力を全方位的にアップグレードされている。 装備関係で注目なのは、先進運転支援技術「プロパイロット」が全車に標準装備されたこと。また、前方の障害物を回避するときにドライバーのステアリング操作を支援する「衝突回避ステアリングアシスト」や、一度駐車した場所を駐車枠として記録することができる「プロパイロットパーキング」を装備するなど、新しい機能も加わり、ドライバーの負担軽減につながっている。 今回の試乗車両は、「チェアキャブ スロープタイプ」(車いす2名仕様/ガソリンモデル)。インプレッションは下記動画を見てほしいが、よりしっかりとしたボディに加え、静粛性を含めた快適性がアップしていることを確認。また、新たにスロープを前倒しにすることができるようになり、通常のミニバンとしても使用できるなどフレキシブルに使えるようになった。 そのほかラインアップが豊富なのもセレナの美点。「車いす1名仕様」もセカンドシート仕様やサード仕様もあり、車いすの代わりにストレッチャーも乗車できるなど、用途にあわせてチョイスすることができる。 日産ライフケアビークル(福祉車両)セレナ 公式サイトhttps://lv.nissan.co.jp/LVCAR/SERENA/ ...
On 2023年8月24日 / By wpmaster文⚫︎Believe Japan 写真⚫︎Believe Japan、トヨタ 2023/8/22(火)配信 今回紹介するのは、バックドア用のロングストラップ「シェイクバンド」(ハイエース車いす仕様車専用)。 これまでバックドアを閉めるとき、つま先立ちしたりジャンプしたりしないと手が届かなかった方は、このストラップ装着することでラクな姿勢で安心して閉めることができる。 標準装着されたストラップとの違いは主に3点。 ⚫︎ストラップ本体の長さを、標準ストラップの248mmから326mmへ76mm延長。⚫︎中間地点にバンドの縫込みがされていて、つねに輪っかが開いた状態になっている。そのため確実に指を通すことができ、力を入れやすい。⚫︎形状を保持するよう工夫されていて、バックドアに挟まらない。ちなみにこれはトヨタオリジナルのアイデア。 ハイエースの大きなバックドアは、閉める際にはけっこうな力が必要。この「シェイクバンド」を装着すれば力も入れやすく、操作時間もグッと短縮できそうだ。 ...
On 2023年8月22日 / By wpmaster文⚫︎Believe Japan 写真⚫︎Believe Japan、トヨタ 2023/8/16(水)配信 車いす仕様車を長く使っていると、ちょっとしたことがストレスになることがある。 今回紹介するのは、車いす乗降時に展開するスロープを、さらに扱いやすくする商品。 車いす仕様車でスロープを展開する場合、その場所が必ずしもフラットな状態とはかぎらない(非舗装路、斜めの場所、砂利道など)ことに目をつけた商品で、スロープの先端にこの「レスステップ」を取り付けるだけで、車いすをラクにスロープに乗せることができるのだ。 価格は1台用(8個セット)で税込8580円。 トヨタ自動車では、「車いすを乗せる場合に、介助される方が受ける振動」が約3割から半分程度に軽減。また「車いすをウィリーなしで乗せる場合に必要な力」も低減してくれるという調査も実施している。 実際に試させてもらったが、車いすを車両に乗せる際のガタつきがなくなり、スムーズに車いすを乗せることができた。 今回の商品はハイエース 車いす仕様車(年式:2004年8月〜)に対応するもので、リフトに固定する際の目印にすることもでき、かなり便利だと感心した。 ...
On 2023年8月16日 / By wpmaster文と写真●Believe Japan 2023/5/15(月)配信 すべての人に自由なモビリティを目指し、製品や技術を紹介するBelieveが注目する福祉車両。前回に引き続きトヨタの人気ミニバンの中から、今回は「ノア」の車いす仕様車に注目し、責任者である野首福利(のくび ふくとし)氏に、開発に込めた想いを聞いた。 広い室内空間とスムーズな乗降を実現! トヨタの「ノア」は、あらゆるシチュエーションに対応する頼もしいミニバン。ラインアップはタイプI「車いす1名仕様(セカンド席)」とタイプI「車いす2名仕様(セカンド席とサード席)」、そしてタイプII「車いす1名仕様(サード席)」があり、タイプIIには標準車と同じシートレイアウトの「サードシート付」仕様が選べる。さらに、このタイプII「サードシート付」仕様には、助手席リフトアップチルトシートを標準装備したタイプも設定されている。撮影車はタイプIの「車いす1名仕様(セカンド席)」仕様だ。 新型モデルは、車いすの乗車から固定までの操作を大幅に簡単にして、操作の時間を半減させている。たとえば、これまで車内のスイッチ操作でリヤの車高を上下させていたが、バックドアの開閉と連動して自動的に車高が上下。後退防止のセーフティモードへの切り替えも自動化され、乗車した車いすのベルトのたるみ取りも必要なくなった。 大きなゆとりに加え、使い勝手が劇的に進化したことで、ノアの快適さはいっそう増している。 バックドアを上げると車高が自動に下がり、簡単に引き出せる手動スロープは角度9.5°と非常になだらか。車いすの乗車から固定まで、一連の動作がとてもシンプルになっている。 室内スペースにゆとりがあるノアは、リクライニング機構が付いた車いすや電動車いす、さらにシニアカーにも対応する(スロープ耐荷重200kg)。「タイプI」はストレッチャーでの乗車も可能。 荷物の取り出しで邪魔となる収納時の「立ったままのスロープ」が、車内に倒れてフラットなフロアとなる「前倒れ機能」も旧型同様に採用されている。 車いすユーザーがコミュニケーションを取りやすい「タイプI」、セカンドシートが標準車同様に使用できる「タイプII」など、使い方に合わせてさまざまなバリエーションが用意される。 関連記事:フルモデルチェンジで乗降操作が簡単に! 大幅進化した新型トヨタ ノア/ヴォクシーの車いす仕様車 新型を開発するにあたり、とくに注力したことを教えてください。 今回ノアの福祉車両について調査をした結果、老老介護をしている女性の方が非常に多いことがわかりました。 そして、旧型ではありますが、問題点などを尋ねると、多かった回答のひとつは「価格が高い」ことと、もうひとつは「操作が難しそうで不安」ということでした。新型の開発にあたって、この2点については確実に改善しなければならないという意識で臨みました。まず価格設定を低めに改めました。ベース車と変わらない感覚で購入できることを目指し、旧型では35万円ほど高くなったものを、グレードによっては10万円アップ位にまで近づけました。そして操作についてですが、おおまかに言えば、操作手順は8回から3回に減り、乗り込むのに必要な時間も120秒から60秒へと半減しています。迷うことなく自然に操作できる、とにかく覚えることが少なくて済むように配慮しました。 機能以外で変わったところはありますか? 旧型との大きな違いでは、新型では新たにハイブリッドを設定しています。これもあくまで普通のクルマであることの証ですが、新型では型式認証を取ることで通常のラインアップとなっています。それにより今までカタログを見たときに、「改造されたクルマ」との印象がありましたが、新型では通常のカタログモデルであることを認識してもらい、福祉車両への心理的なハードルをまたひとつ取り除くことができたと思っています。... ...
On 2023年5月15日 / By wpmaster文と写真●Believe Japan 2023/5/12(金)配信 超高齢化社会に突入して久しい日本では、近年、在宅介護が推奨されている。そして、そうしたなか、 自宅からデイケア施設や医療機関へ通う高齢者が増え、 福祉車両の使用頻度は、これまでになく高まっている。 「すべての人に自由なモビリティ」を紹介するBelieveが今回注目するのは、トヨタの新型シエンタ「ショートスロープ仕様」。開発責任者である稲熊幸雄(いなぐまゆきお)氏に、そのこだわりのポイントを聞いた。 ショートスロープで、乗り入れ動作をシンプルに! 両側スライドドアに広々とした室内、低床設計でアクセスが良好なトヨタシエンタは、2022年8月にフルモデルチェンジして3代目となった。ビリーヴカー(福祉車両)は3タイプあるが、もっとも注目したいのがタイプIIIの「ショートスロープ仕様」。バックドアを開けると同時に車高が降下し、リヤバンパーと一体型のショートスロープが展開。リアエンドからスロープが突出する長さはわずか17cmで、省スペース&短時間での乗降を可能とする。 バックドアを開けると自動的に車高が下がる。そして、ショートスロープが展開。 車いすの前輪をショートスロープに乗せ、後輪をスロープに押し当てながら車内へと進む。 車いすの前後左右にフックをかけて固定スイッチを押す。あとはハンドルを引いてショートスロープを収納、バックドアを閉めれば自動的に車高が戻る。 関連記事:難点だった乗り込み時間を大幅に短縮! 新型シエンタの「ショートスロープ」がすごい シエンタ福祉車両開発時のこだわりを教えてください 現在、福祉車両のシェアはトヨタが日本国内の約7割を占めています(除:軽自動車)。そのため、我々には「スタンダードを作っている」という自負があります。 「トヨタでしかできない福祉車両の在り方とは何か」をつねに意識し、介護施設などでお客様のご使用になっている様子から本当の困り事はなにか見極め、自分たち自身で仮説を立て検証して開発しています。また、標準車との同期開発やインライン生産対応などのコスト低減も積極的に実施しています。 今回の新型シエンタ タイプIII「ショートスロープ仕様」で改善したのは、以下の3つの点です。 まずひとつ目は「車いすにお乗りの方の孤立を防ぐ」ことです。 たとえば病院のエントランス。迎えにきたドライバーがクルマを離れ戻ってくると、別のクルマがすぐ後ろに停めてしまい、車いすで乗り込むことができないという事態があります。今までの福祉車両では、車両の後方に2.4メートルのスペースがないと乗り降りできませんでした(通常、停車している前のクルマとの間隔は、1.7メートルほど)。ところがこのショートスロープ版では1.3メートルあれば乗り降り可能ですから、クルマを移動させなくてもよくなります。これまで車いすユーザーの方は、ドライバーがクルマを移動させて戻ってくるまでの間、そこに一人で待たなければなりませんでした。認知症の方がブレーキを外して、後ろのクルマにぶつかったり、どこかに移動してしまうなどのトラブルも報告されています。そのような事態を改善したいと考えました。... ...
On 2023年5月12日 / By wpmaster文と写真●Believe Japan 2023/3/31(金)配信 介助する側、介助される側、双方の立場になってビリーヴカー(福祉車両)をインプレッション! レポートするのは、介護経験があり自身も福祉車輌取扱士スペシャリスト資格を持つタレント・モータージャーナリスト 竹岡 圭。今回は、ホンダ ステップワゴン スパーダ 車いす仕様車〈2列目乗車タイプ〉をご紹介します。 ホンダ福祉車両:https://www.honda.co.jp/welfare/ ...
On 2023年3月31日 / By wpmaster文と写真●Believe Japan 2023/3/15(水)配信 2022年5月に登場して人気を集めている6代目ステップワゴン。その改良点の多くは、福祉車両としての使い勝手や快適性に直結するものが多く、ビリーヴカー(福祉車両)としても注目のモデルだ。今回は「車いす仕様車」をチェックして、その実力を探った! 1996年にファミリームーバーとして誕生して初代以来、ステップワゴンは家族みんながくつろげる広々とした室内空間を標榜してきた。6代目となる最新モデルでは、「国内ホンダ車史上最大の室内空間」を掲げている。 福祉車両にも生かされる新型ステップワゴンのレベルアップ 車いす仕様車は、2列目に車いす乗車するタイプ、3列目に乗車するタイプ、2列目と3列目に車いす2台で乗車するタイプの3タイプが設定されているが、このクルマは2列目に乗車するタイプ。新型ステップ ワゴンの福祉車両は全車「スパーダ」をベースにしている。先代モデルから受け継ぐ3列目の分割床下格納シート「マジックシート」とフローリングフロア、電動ウインチに加え、パワーテールゲート(メモリー機能付き)が福祉車両に全車標準装備されているが、 各部さらに改良が加えられている。 ・「安心」と「自由」を表現したというスタイリングは、クルマ全体的に凝縮感、カタマリ感があり、シンプルでスタイリッシュなデザインからは、使いやすさや機能性が感じられる。・「国内ホンダ車 史上最大の室内空間」というキャッチフレーズだが、全席で快適な居住性を誇る。・ 搭載されている1.5L直噴VTECターボエンジンは力強く、車体は走行中の振動が抑えられ静粛性も高められている。車内での会話がより快適になっている。・車両感覚をつかみやすい視界のほか、サイドウインドウの下端を前後水平にし、1列目より2列目、さらに3列目と着座位置を高くするなど、乗り物酔いをしづらくする工夫も施されている。最新の安全運転支援機能も標準装備される。 気軽に出かけたくなる抜群の乗降性 スロープはスロープ脇にあるロックを引っ張って展開する。 スロープにはダンパーが取り付けられていて、ロックを引いてもスロープが急に倒れていたりする事はなく、安心の設計となっている。スロープは力を必要とせずスムーズに伸ばすことができる。 画期的なのは3列目シートの収納。ショルダー部分についたベルトを上に軽く引っ張るだけで、シートは畳み込まれストンと床下に収まる。 思わずあっけにとられてしまう素早さだ。そしてシート裏とスロープのパネルを展開すれば、車いす乗車ができるフラットなフロアができあがる。一般的な福祉車両では3列目シートを窓側に跳ね上げる構造のため、車いすで乗車すると両側面の視界が遮られてしまうが、ステップワゴンでは3列目シートが床下に収納されるので、車いすで3列目に乗車しても車窓からの景色を楽しめる。また、3列目でも車いすの横に乗車することもできる。 続いてウインチをリリースするボタンを押し、車内にあるベルト(2本)を持ってきて車いすに取り付ける。 次にリモコン操作をすると自動で車いすを車内に引き込んでくれる。ウインチの対応重量は120kg、スロープの許容重量は200kgと大柄な車いすユーザと介助する方でも安心して使える設計だ。 車いすの固定もベルトでしっかりと行えて乗り込み動作は簡単だ。... ...
On 2023年3月15日 / By wpmaster文と写真●Believe Japan 2023/3/8(水)配信 東京青山にあるホンダ本社のショールーム「Honda ウエルカムプラザ青山」で2月に開催された福祉車両企画展示「Honda ハート Joy for Everyone」で注目の福祉車両をチェックしてきた! 普段、F1やMotoGPなどホンダが参戦してきたレース車両などが並べられるホールには、ステップワゴンの車いす仕様車やサイドリフトアップシート車、N-BOX車いす仕様車、フィットテックマチックシステムなどの福祉車両が展示され、多くの来場者が訪れていた。また、展示イベントの終了日前日には、現役引退を表明したばかりのプロ車いすテニスプレーヤー国枝慎吾氏のスペシャルトークショーも実施された! ステップ ワゴン 車いす仕様車/サイドリフトアップシート車 2022年5月に登場した6代目ステップワゴンだが、 その改良点は福祉車両としてのクオリティを大いに高めるものばかりだ。 ・「安心」と「自由」を表現したというスタイリングは、クルマ全体的に凝縮感、カタマリ感があり、シンプルなデザインからは使いやすさや機能性が感じられる。 ・「国内Honda車 史上最大の室内空間」というキャッチフレーズの室内は全席で快適な居住性を誇る。 ・車両感覚をつかみやすい視界と乗り物酔いをしづらくする工夫、さらに最新の安全運転支援機能が標準装備される。 新型ステップ ワゴンの福祉車両は「スパーダ」をベースに、車いす仕様車とサイドリフトアップシート車が設定される。先代モデルから受け継ぐ3列目の分割床下格納シート「マジックシート」とフローリングフロア、電動ウインチに加え、パワーテールゲート(メモリー機能付き)が福祉車両に全車標準装備されている。... ...
On 2023年3月8日 / By wpmaster文●Believe Japan 写真●日産 2022/12/9(金)配信 1991年に発売して以来、ファミリー層を中心に広く支持されてきたミニバン「日産 セレナ」がフルモデルチェンジした。新型で注目したいのは、日産のビリーヴカー(福祉車両)となる「ライフケアビークル」で、ついに人気の「e-POWER」がすべてのモデルで選べるようになったこと。これまで標準モデルでは、エンジンとモーターが連動して静粛性の高い走行や低燃費を実現するe-POWER搭載車が高い人気を誇っていたが、福祉車両での設定は限定的であった。 新型のe-POWERは、新たに開発された1.4Lの専用エンジンを組み合わせた第2世代で、エンジンの作動音を抑制し、よりパワフルでスムーズな加速性能を実現。また車両状態や走行環境に加え、ナビと連携しながらエンジン作動タイミングを制御するエネルギーマネジメント技術を搭載。結果、高い静粛性を発揮する。さらに車体の遮音性能を大幅に高め、後部座席の乗員との自然な会話がしやすくなった。運転支援技術「プロパイロット」もすべてのモデルで標準装備となり、安心感も増している。 e-POWERモデルは、100V AC電源(1500W)が新たにオプション装備となり、アウトドアにおける家電製品の仕様や災害時等の非常用電源としても使えるようになっている。そのほかさまざまなレベルアップを遂げている新型セレナは、以下のように多彩なタイプの福祉車両が設定されている。 助手席スライドアップシート/セカンドスライドアップシート 助手席、または2列目左側シートが、車両の外側に電動で回転、昇降することで、車への乗り降りが容易にできるタイプ。スライドアップシートには、シート回転や昇降に加え、シートスライドとリクライニングの操作も可能としたリモコンを標準装備。また、回転や昇降の速度も変更できる。 チェアキャブ スロープタイプ セレナの広さや使い勝手の良さを生かし、バックドアから車いすのまま車内に乗り込めるよう、手動式のスロープや車いす電動ウインチ、車いす固定装置が装備される。車いすの方が2列目左側に乗車する「車いす1名セカンド仕様」はじめ、使い方に合わせて全4種類のレイアウトから選べる。新型ではバックドア部のスロープの格納方法を改良し、3列目に車いすが乗車しないときには荷物スペースとして使用できるほか、車いす乗降時の操作スイッチがよりシンプルとなり、操作性が改善されている。 チェアキャブ リフタータイプ リモコン操作で昇降する全自動リフターを装備し、車両後部から車いすのまま車内に乗り込めるタイプ。車内に乗り込む前にリフター上で車いすの固定が可能なため、介助者の負担が軽減されている。新型では、オプションの車いす固定装置(電動式)のフックを、従来の一体型から分離式に変更し、さまざまな種類の車いす固定に対応している。 送迎タイプ 福祉施設や病院などの送迎時に、利用者がスムーズに乗降ができるよう工夫したタイプ。2列目に専用形状シートを採用し、助手席側スライドドアから3列目シートへの乗降性を向上させ、乗降用手すりやステップを装備することで、高齢者や足元に不安を感じる方でも乗降しやすくなっている。ステップは、助手席側スライドドアから乗降する方に加え、助手席でも同時に使えるロングステップを新たに採用し、乗降性をさらに向上させている。 乗降サポートパック付車 新型で新たにラインアップされたタイプ。ベース車のシートレイアウトはそのままに、乗降時や各シート乗車時に使用できるアシストグリップを標準装備し、福祉施設や病院のみならず、ホテルや旅館などの送迎ニーズにも対応する。... ...
On 2022年12月9日 / By wpmaster© 2016-2020 Believe Japan, Inc. All rights reserved.