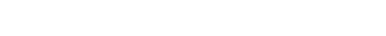2025/3/10(月)配信 WHILL株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長 CEO:杉江理、以下「WHILL社」)は2025年4月16日~18日にインテックス大阪で開催される「バリアフリー2025(第31回 高齢者・障がい者の快適な生活を提案する総合福祉展)」(以下「バリアフリー展」)に出展することを発表した。会場では、2025年4月から介護保険適用対象となるWHILL社最新機種のスマートになった歩道のスクーター「WHILL Model R」のお披露目に加え、会場内アクセシビリティ整備の一環として近距離モビリティWHILL(ウィル)を気軽にレンタルできる「WHILLモビリティサービス」の提供、地域リハや自立的な生活支援などをテーマとするリハビリ従事者向けセミナーの開催などを行う予定という。WHILL社は「ウィルでつながろう」をコンセプトとする一連の取り組みを通じ、リハビリや介護福祉の業界に関わる方々と一緒にこれからのリハビリのあり方を考えながら、人や地域との連携を深め、ウィルも当たり前に走る健康で幸せな未来の形を会場全体で提示するとしている。 WHILL公式サイトバリアフリー展2025 公式HP ...
On 2025年3月10日 / By wpmaster文⚫︎大音安弘 写真⚫︎Believe Japan 2023/6/26(月)配信 次世代型電動車椅子を手掛けるWHILLの最新モデルが、「Model S」だ。これまでの車椅子タイプとの最大の違いは、電動スクータータイプであること。免許返納者などを含む手軽なシニア向けモビリティを目指して開発された。ターゲットとなるのは、少し距離がある場所への徒歩を負担に感じるようになった人や、手軽な移動手段を求める免許返納者だ。 シニア向け電動カート同様に、安定した着座姿勢が得られるシートと、シンプルな操作が可能なバータイプのステアリングを装備する。操作系はステアリング周辺に集約されており、ステアリング内のレバーを握ると、カートが動く。レバーを放せば、ブレーキがかかる仕組みだ。アクセルとブレーキの役目を持つレバーは、右側が前進、左側が後退と分けれて、操作の誤りを防ぐ。走行速度は、ハンドル内中央のパネル上のダイヤルで簡単かつ細やかな調整が可能だ。またバッテリー残量をバータイプの表示で見やすいものとした。操作は、自動車の操作や表示に近いものを目指したという。 最高速度は、前進で6km/h、後退で2km/hのため、歩道走行も可能。段差は、7.5cmまで乗り越えることができるので、街中である車道と歩道のギャップも問題なし。登坂能力も10度となるので、日常的に遭遇する多くの傾斜路に対応できる。航続距離は、満充電で33kmと長め。ちょっと離れた場所への買い物や移動も叶えてくれるのも強みだ。充電時間は標準充電器で9時間40分だが、オプションの急速充電器を用いれば6時間40分まで短縮できる。また乗員重量だが、100kgまでとなるので多くの人が利用可能だ。 デザインは、従来のシニアカーと比べるとお洒落なもの。シンプルなデザインに仕上げカラーリングにも拘ることで、だれでも気軽に使えるモビリティを目指したという。もちろん、機能性も重視されており、フロントに耐荷重4kgのバスケットを標準化。さらにオプションで耐荷重1kgのフックを始め、後方確認用の左右ミラーや杖ホルダーなどのアクセサリーも用意されている。 安心安全な移動を提供するために、もしものアクシデントに備えるロードサービスと任意保険を用意。スマートフォン連携機能では、バッテリー残量や移動可能距離の確認、車両設定が行えるが、「Model S」で新たに採用された車載通信機を搭載することで、現在地確認に加え、走行ログも自動的に記録。家族による現在位置の確認はもちろんのこと、「Model S」が転倒した際に、家族に緊急通知する機能も備えている。使用者だけでなく、家族にも情報が提供することで、外出しやすい環境作りにも貢献する。 価格は22万7000円となり、消費税は非課税。ただし介護保険は適用外だ。 関連動画 WHILL公式サイトhttps://whill.inc/jp/ ...
On 2023年6月26日 / By wpmaster文⚫︎大音安弘 写真⚫︎Believe Japan 2023/6/22(木)配信 次世代電動車椅子メーカーであるWHILLの「Model F」は、簡単に折り畳めることで、幅広いシーンでの活躍が期待できる電動車椅子だ。 折り畳みよるコンパクト化のメリットは、自宅での保管場所の自由度を増すだけでなく、自動車や列車などほかの移動手段との組み合わせることで、行動範囲を広げることができる。重量も約27kgに抑えられているため、自動車の車内やトランクにも載せやすい。また本体も小型なため、半径78cmで回転できる小まわり性のよさを備えており、建物内などのかぎられた空間でもスムーズな移動を実現している。 一見、簡易的な電動車椅子に見えるかもしれないが、基本性能は十分なものを備えている点も見過ごせない。充電は5時間で満充電となり、20kmの走行可能距離を確保。移動速度は最高6km/hなので、歩道も走行できる。もちろん、運転免許は不要だ。小型化によりタイヤサイズが小さいことから、段差乗り越え能力が3.5cm、登坂能力が10度となるが、街中ならば、概ねクリアできる能力を持つ。また乗員の耐荷重についても、115kgまでとなっており、多くの人に対応できるのも強みだ。 運転操作は、車体アームレストの前方にあるコントローラーで行う。コントロールパネルの位置は、左右を交換可能。右利きと左利きに配慮した設計となっており、ユーザーが運転しやすい操作系を実現している。操作方法もシンプルだ。走行時は、進行方向にコントローラーをスライドさせるだけ。コントローラーから手を放すとブレーキが掛かる。専用アプリでスマートフォンと連携させると、バッテリー残量や航続距離の確認をはじめ、車両のロックと解除、車両設定が行える。 さまざまなオプションも用意されており、車両のロックと解除を行えるリモコンキーをはじめ、着せ替え可能な5色のボディパネル、シート下のバスケット、スマートフォンホルダー、ドリンクホルダー、杖ホルダーなどがあり、楽しい移動をサポートしてくれる。またもしもの際に、自身だけでなく相手への補償を行う保険やロードサービスなども選ぶことができる。 価格は、27万3000円で消費税は非課税となるが、介護保険の適用外となる。また機動性の高さから旅行などにも活用してもらえるように、WHILLによる短期間のレンタルプランも用意されている。まずはWILLのある生活を体験してみたいという人にもオススメだ。 関連動画 WHILL公式サイトhttps://whill.inc/jp/ ...
On 2023年6月22日 / By wpmaster文⚫︎大音安弘 写真⚫︎Believe Japan 2023/6/21(水)配信 次世代電動車椅子を手掛けるWHILLの近距離モビリティ「Model C2」は、介護保険にも適用する幅広いシニア層の安全な外出をサポートする一台だ。2017年より発売された「Model C」の改良型として、2020年より販売されている。 進化のポイントは、大きく5つある。一つ目は、乗り心地の向上だ。リヤサスペンションを採用することで、段差の乗り降りやデコボコした道でも衝撃を吸収することで快適な走りを実現している。二つ目は、コントローラとスイッチの改良だ。コントローラとスイッチを片側に集約し、運転も軽い力で行えるようにすることで操作性を向上。またコントロールパネルは、ユーザーの好みで装着位置を左右に付け替えることができるようになった。三つ目が、航続距離の拡大。2km拡大の18kmとしている。四つ目は、夜間での後方からの視認性の向上だ。テールランプ位置を変更することで、シートバックにリュックサックを掛けた状態でも、しっかりとテールランプが確認できるようになった。五つ目は、アームレストの跳ね上げ性能を改善することで、乗降時のアクセス性がよくなり、ベッドや椅子などの真横から乗り降りする際に、よりスムーズな移動が可能となっている。 走行性能は、フロント部にオムニホイール(全方位タイヤ)を採用。複数の車輪から構成する構造により、縦だけでなく横方向の移動も可能としたもので、5cmの段差乗り越え能力に加え、コンパクトな「Model F」よりも小さい76cmの最小回転半径を実現。しっかりとした車椅子形状ながら、建物内などの狭いスペースでも小まわり性のよさを見せる。対応の傾斜角度は10度を有しており、多くのシーンで安心の移動を提供してくれる。最高速度は、前進6km、後退2kmとなり、歩道走行が行える。運転方法も簡単で、グリップを進行方向にスライドさせるだけだ。もちろん、運転免許は不要となる。充電は、専用普通充電器を使い5時間で満充電に。航続距離は上記にあるように18kmとゆとりあるもの。また最大荷重も115kgとなるので、多くの体形の人に対応できる。 機能面の特徴を紹介すると、可動式アームレストの採用で横方向からの乗り降りも可能に。電動車椅子ながら、分解可能な構造となっており、自動車に積載することもできる。買い物やお出かけの際の荷物を収納できるシート下の20Lのカゴも標準装備となる。専用アプリで、スマートフォンとの連携が可能で、車両設定が可能なほか、遠隔操作で自身の元まで「Model C2」を運ぶこともできる。 オプションも豊富で、気分に合わせて着せ替え可能なアームカバーを始め、ドリンクホルダーやスマートフォンホルダー、骨盤ベルト、杖ホルダー、スマートキーなどを用意する。また他モデル同様にアクシデントの際、自身の怪我だけでなく相手側の補償までカバーする専用保険やロードサービスも用意されている。 価格は48万7000円となり、消費税は非課税となる。また月額のレンタルプランも用意。さらに介護保険を利用すれば、手ごろな価格でレンタルすることができる。 関連動画 WHILL公式サイトhttps://whill.inc/jp/ ...
On 2023年6月21日 / By wpmaster文と写真●Believe Japan 2023/6/9(金)配信 介助する側、介助される側、双方の立場になってビリーヴカー(福祉車両)をインプレッション! レポートするのは、介護経験があり自身も福祉車輌取扱士の資格を持つタレント・モータージャーナリスト 竹岡 圭。今回は、番外編としてWHILLの車いす「Model C2/F/S」3モデルをご紹介します。 価格など詳しい情報はWHILL公式サイトをご覧くださいhttps://whill.inc/jp/ ...
On 2023年6月9日 / By wpmaster文と写真●大音安弘 2022/9/21(水)配信 近距離モビリティを提供するWHILLは、2022年9月13日、歩道を走れる電動スクーター「WHILLモデルS」の先行受注を開始したことを発表した。価格は、21万8000円から(非課税)となる。 「モデルS」は、バータイプのグリップハンドルを備えた4輪電動スクーターだ。最高速度6km/h(後退時2km/h)で走行し、7.5cmの段差乗り越え能力と10度の登坂能力を備え、歩道走行が可能。航続距離も実用性の高い33kmとしている。取り外し可能な鉛電池を装備し、充電時間は標準充電器の場合9時間40分、急速充電器で6時間40分となっている。モデルの魅力としては、高齢者向け車両のイメージを払しょくするシンプルかつお洒落なデザインと、自動車の操作感覚を意識したインターフェイスなどがあげられる。また専用車載通信機「WHILL Premium Chip」の搭載による通信アプリ「WHILL Familiy App」による新サービスにも対応し、「位置情報の確認、外出履歴の記録、家族への情報通知」などを行えるようにした。「WHILL Premium Chip」の搭載には別途2万5000円(非課税)が必要となり、サービス利用には「WHILL Premium Care」の契約が必要となる。年間サービス料は2万6400円(税込)となり、これには専用アプリに加え、ほかのWHILLでも提供する保険、ロードサービス、メディカルアシストのパッケージ「WHILL Smart Care」が含まれる。 ターゲットユーザーは、日常生活に支障はないが買い物などの移動手段に困る人たちだ。これまでWHILLは、建物内の移動も想定した電動車イス型の短距離モビリティを提供してきたが、それよりもライトな存在なのがこの「モデルS」だ。自転車の運転がふらついてしまう体力的に不安があるユーザーに、自転車以上自動車未満の存在として提供する。現在、65歳以上の高齢者は3600万人にものぼり、そのうち1000万人が歩行に対する不安や制約を抱えているという。その一方、WHILLがアンケートを実施した免許返納した70~80代のシニア世代の男女100人のうち、三人に一人がクルマの変わりになる移動手段が少ないと回答しており、彼らをサポートする新たな移動手段の必要性を強調する。事実、昨今の免許返納者は年間60万人前後で推移しており、彼らは移動手段をクルマやバイクなどから切り替えていることになる。さらに2022年5月13日より一定の違反歴のある高齢ドライバーを対象とした運転技能検査が義務化され、運転免許の更新ができない人たちが増えてくる可能性も高まっていることもあり、今後「モデルS」のような電動スクーターのニーズは高まっていくと予測される。 電動車いすタイプの「モデルCS」など派生仕様も検討中 WHILL事業開発戦略室の赤間 礼氏によれば、「ある程度の歩行が可能な人たちは、電動車イスには抵抗があり、自分に合った乗り物だとは感じてもらえない。そこで電動スクーターという形状とし、自動車からの乗り換えを意識した自動車に近い操作性を与えている」とし、価格面でもリーズナブルに提供できるように、設計や調達からも工夫を凝らすことで、既存のセニアカーと比べても競争力のある価格を実現させたとしている。新たな取り組みである車載通信機「WHILL Premium Chip」は、スマートフォンを持たないユーザーを意識したものだそう。アプリで情報共有を家族と図ることで、ユーザーが「モデルS」を使うことの安心を提供したいという願いも込められている。今後の展望としては、まずはエントリーとして「モデルS」を活用してもらい、その後のライフステージに合わせ、電動車イスタイプの「モデルCS」や「モデルF」といった最適なモビリティを選んでもらい、長くWHILLを愛用してもらえるようになればと期待を込めた。... ...
On 2022年9月21日 / By wpmaster文●Believe Japan 写真●WHILL クルマの世界では自動運転技術が大きく進化し、今日、世界中のメーカーがその開発にしのぎを削っている。「自動運転」は高性能なセンサーやカメラ、電子制御技術によってドライバーの運転をサポートするもので、事故の減少やドライバーの疲労軽減、交通渋滞の解消などが期待される。 一方、近年電動化がめざましい車いすの分野でも、自動運転技術がついに登場した。毎年1月に世界中から最先端の技術が発表されることで知られる「CES(セス)」。アメリカのラスベガスで開催される世界最大といわれる電子機器の見本市で、今回ひときわ大きな注目を集めたのが、空港をはじめとする商業施設などでの導入を見据えた「電動車いすの自動運転」だった。「WHILL自動運転システム」と名付けられたコンセプトを発表したのは、スタイリッシュなデザインでだれもが手軽に操作できる電動車いすを開発するWHILL(ウィル)。斬新なアイデアによって世界中から幅広い支持と投資を集め、意欲的な活動を展開している、神奈川県横浜市に拠点を置くベンチャー企業だ。 多くの人が行き交う空港や大規模な商業施設では、手動、電動にかかわらず車いすユーザーは障害物や人との接触を避けながら、目的地までのアクセスを確認して移動しなければならない。とくに空港では、搭乗時刻が迫っている乗客などが小走りで移動したり、スーツケースやカートなども行き交うため、車いすでの移動は大きな心労を伴う。 今回WHILLが提案する自動運転の車いすシステムは、初めて電動車いすを操作するという方でも不安なく移動できるように設計されている。もともと直感的な操作によって移動できることが魅力だったウィル各モデルに自動停止機能が付き、ユーザーが認識しない障害物との接触を防ぐことができるようになっている。車いす利用者のさらなる増加が見込まれる空港においては、今後深刻な混雑が予想されているため、車いすの自動運転化はその有力な解決策としても注目を集めそうだ。 自動停止、自動運転を行うパーソナルモビリティは、周囲の歩行者との距離を計算、柱などの障害物を想定し、周囲全体を視野に入れる必要がある。この車いすには前方と側方を監視するためのステレオカメラが、左右のアーム部分に1個ずつ装備され、広い視野角度を実現している。後方にはセンサーが備わり、後退の際の衝突防止にも配慮。 周囲の状況を検知し、その情報とあらかじめ収集した地図情報を照らし合わせ、安全に自動走行を行う電動車いす。それぞれが通信回線を搭載することで、どの場所にどの車いすがあるかが常に把握でき、サービスの運用負担が大幅に軽減される。さらにユーザーが乗り終えると、自動で保管場所まで戻るため、回収にかかっていた人件費を減らすこともできるなど、導入、実用化のハードルを下げるための工夫が随所に施されている。 乗車しながら運転状況を確認できるタブレット端末や背面のスーツケース格納するアタッチメントが装着されたタイプ。提供される「車いすを自分がいる場所まで呼び寄せるアプリ」は、使用シーンに合わせて施設側が柔軟に改良することもできるという。 WHILLでは今後の展開について、3段階での進行を予定している。 【現在】ハードウェアとしての電動車いすと開発に必要なオプションやライブラリの提供が可能。自動運転システムを開発できるパートナー企業や、カメラやセンサーなどの研究を行う大学などへ、研究開発モデル「Model CR」として提供を行う。 【2020年の実用化】空港、商業施設、博物館や美術館、駅などにおいて、シェアリング事業を行うパートナー企業を想定。モビリティの提供および自動運転システムの開発はWHILLが行い、モビリティプラットフォームや支払いシステムなどの構築はパートナー企業が担当する。 【2020年以降の実現】モビリティの提供から、フロントエンドシステムまで、すべてWHILLが提供。自治体など特定のエリアにおいて、WHILLがシェアリング事業を行う。 WHILL自動運転システムは今回のCES 2019で、Accessibilityカテゴリーで最優秀賞を受賞するなど、大きな注目を集め、高く評価された。今後多くの空港での導入が見込まれ、オランダのスキポール空港やイギリスのヒースロー空港、アメリカのラガーディア空港においては、実用化に向けた検討がすでに開始されている。また、空港以外でも積極的な導入を目指しているWHILLでは、小田急グループやスポーツ施設、商業施設での実用化も順次進めていく考えを明らかにしている。 新しい移動のスタイルを提案するWHILLは、2012年5月に日本で創業し、2013年4月にはアメリカ、2018 年8月にはオランダに拠点を設立。世界全体で約200名のスタッフが、「すべての人の移動を楽しくスマートにする」ことを目標に活動している。 ...
On 2019年1月18日 / By wpmasterパーソナルモビリティブランド「WHILL」の電動車いすは、洗練されたデザインや手軽な操作性、優れた走行性能で高い人気を集めているが、それは日本だけには止まらぬようだ。 このほどアメリカのネバダ州ラスベガスで開催された、コンシューマエレクトロニクス(家庭用電気機械器具)分野で世界最大級の見本市となる「CES 2018」において、WHILLの電動車いすが「Best of Innovation Award(ベストオブイノベーションアワード)」を受賞した。選ばれたのは、日本で2017年にリリースされている電動車いす「WHILL Model C(ウィル モデル シー)」の米国向けモデル「WHILL Model Ci(ウィル モデル シーアイ)」。革新的なデザインや操作性、小まわり性能、iPhoneアプリによる遠隔操作機能、さらにカスタマーサービスに「IoT」を活用した点などが高く評価されたという。ここではModel Cの魅力を改めて紹介する。 WHILL Model C WHILLはModel... ...
On 2018年1月9日 / By wpmaster文 ●Believe Japan 写真●北川泉 「乗ってみたい!」。ひと目見てそう思わせる車いす。 電動車いすの「WHILL」は、まずそのカタチで語りかけてくる。見るからに未来的で洗練されたデザインは、理屈抜きに「乗ってみたい!」と思わせるものだ。発売開始以来、大きな反響があるというのもうなずける。 そしてこのWHILL「Model A」は、見た目がおしゃれなだけではけっしてない。コンパクトなボディには、高い機能性と快適さが込められている。24個の小さなタイヤで構成される「オムニホイール(全方位タイヤ)」は、独自に開発されたもので、「4輪駆動」と相まって、細い路地、砂利道、芝生、でこぼこ道など、悪路の走行を可能にし、高さ7.5cmの段差を乗り越えることもできる。いままでなら「ここで待ってるから……」と躊躇していた場所にも、臆することなく進んでいけるのだ。 屋内用、屋外用、レジャー用というように、用途に合わせて何台ものパーソナルモビリティを使い分ける必要はなく、WHILLが1台あれば、さまざまな場所へ行くことができる。その可能性の広がりは、ユーザーの気持ちを大いに解放してくれることだろう。 「100メートル先のコンビニもあきらめる」の言葉に挑んだ 杉江 理さん、内藤淳平さん、福岡宗明さんという3人の若者を中心に、2012年、利用者に優しい「車いす」の開発を目指して設立されたベンチャー企業「WHILL」だが、そのきっかけとなったのは、彼らが神奈川県のリハビリテーションセンターを訪れた際に聞いた車いす利用者の「100メートル先のコンビニも諦めてしまう」という言葉だったという。それは、たった100メートルというわずかな距離であっても、「ちょっとした段差が乗り越えられない」、「砂利道があって走れない」といった、悲痛な訴えだったという。また、物理的なバリアだけでなく、車いすで出かけることへの億劫さや不安といった心理的なバリアも存在するという。 電動車いすWHILLは、これらのバリアを克服し、スマートで機能的な新しい「パーソナルモビリティ」を目指して開発されたという。 サイズ(Model A)は、長さ89cm(前後スライドによる) x 幅60cm x 高さ90cm、重量は:116kg。約9時間程度でフル充電し、最大約20kmの走行が可能だ。最大10°の登坂力がある。 WHILL。神奈川県横浜市にある日本本社を訪れてみて、実際にWHILLに触れ、試乗させてもらった。初めてにもかかわらず、ほぼ自分の思いどおりに動く、そのしなやかな挙動に感銘を受けた。前後左右、そして斜め方向にも、リニアに移動してくれるのだ。数分も乗っていると自分のカラダに馴染んでくる感覚になる。 最高時速は、歩道を走行できる制限の6km。レバーで時速4kmに制限することも可能で、歩行者の隣を走るのに便利な機能となっている。「子供の送り迎えを、手をつなぎながらできるようになりました」というお母さんユーザーからの喜びの声も届けられたという。... ...
On 2016年12月14日 / By wpmaster© 2016-2020 Believe Japan, Inc. All rights reserved.