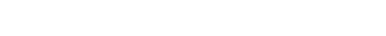文と写真●Believe Japan 2025/12/25(木)配信 車いすユーザー自らがハンドルを握りドライブできる、Self-empowerment Driving Vehicle(セルフエンパワーメント ドライビング ビークル、以下SeDV)。マツダが初めてSeDV仕様を導入したのは2022年、クロスオーバーSUVの「MX-30」だった。そして2025年、より幅広い人たちに応えるべく、「CX-30」にも設定されることとなった。CX-30 SeDVは、頃合いのいいサイズ感と実用性、そして美しいスタイリングをバランスさせたクロスオーバーSUVで、その存在は先ごろのジャパンモビリティショー2025でも多くの注目を集めていた。 リング式アクセルとレバーブレーキがもたらす直感的な操作性 CX-30 SeDVの主役は、ステアリングの内側に配置されたリング式アクセルと、ハンドル左側に設置されたレバーブレーキである。運転操作は、リングを押し込むことで加速。押し込む量に応じて段差感を持たせ、速度の維持や細かな調整がしやすいよう配慮されている。そのため、交差点進入時や駐車時、立体駐車場のスロープなど、繊細なコントロールが求められる場面でも、スムーズで自然な挙動が得られるのが特徴だ。 一方のレバーブレーキは、肘を支点として操作できるようブレーキサポートボードが装備されており、操作の安定性と疲労軽減を両立している。押し込むだけの操作で制動できるため、体幹が弱っている人でも、無理のない姿勢で確かな剛性感と自然な制動フィーリングが得られ、確実なブレーキ操作が行える。 従来の福祉車両で一般的だった「ハンドルにノブを取り付け、片手でハンドル操作、もう片方でレバーによるアクセル&ブレーキ操作」というスタイルとは異なり、両手でハンドルを握ったまま自然に加速操作ができ、よりダイレクトかつ繊細な感覚でブレーキを扱える。このため、通常の運転に近い姿勢で走行でき、違和感の少ないドライビングが可能となる。長時間の運転でも疲れにくく、初めて手動運転装置に触れる人でも短時間で操作に慣れる完成度を備えている。 家族とのシェアができる「手動/通常運転」の簡単切り替え SeDVの大きな特徴は、手動運転と通常のペダル運転を簡単に切り替えられる点だ。これなら、家族や友人とのドライバー交代も容易である。手動運転モードでは、レバーブレーキを前方へ押し込んでロックし、その状態でイグニッションを入れることでアクセルペダルが無効化され、リング式アクセルによる加速が有効となる。反対に通常運転への切り替えは、フットブレーキを踏み込んだ状態でイグニッションを入れるだけでよく、特別な操作を必要としない。このシンプルな切り替え方式により、手動運転装置は「特定の人だけが使う特殊機能」ではなく、家族全員で共有できる「運転方法のひとつ」として成立している。 車いすは助手席側後席に 車いすは助手席側後席に載せる方式である。まず助手席の背もたれを前方へ倒し、続いて運転席の背もたれを後方へ倒す。この助手席前倒しレバー(オプション)は運転席側から操作できるよう配置されており、乗車位置を変えることなくシート調整が可能。車いすは折り畳んで引き上げ、ドライバーの身体の上を通す形で助手席側後席へ積載する。また、車いす利用者が助手席へ移乗し、他の人が運転する場合を想定し、シート調整レバーは通常どおり助手席側にも備えられている。移乗ボードも助手席側に設置することも可能だ。... ...
On 2025年12月25日 / By wpmaster文と写真●Believe Japan 2025/11/22(土)配信 日本最大の福祉機器展「H.C.R.(国際福祉機器展)」に今年も行ってきました! ここでは自動車部品メーカーのJATCOが開発した移乗機構付き車いすをレポートします。 世界各国の自動車メーカーに対し、主に自動変速機(AT)の開発・製造を手がけてきたパワートレイン専門メーカーであるJATCO(ジヤトコ)が、初めて福祉機器分野に本格参入する。その第一弾が、今回の福祉機器展に出展した移乗機構付き車いす「Lifmy(リフミィ)」である。介護の現場では、車いすやトイレなどへ移動してもらうため、ベッドに横たわる人を抱え上げて立たせるという動作が、肉体的にも精神的にも極めて大きな負担となる。Lifmyは、まさにこの課題に対する有力な解決策として注目を集めている。 移動の難関「立ち上がり」をしっかりサポート 被介護者の方の残存筋力を積極的に活用することを前提に「Lifmy」が立ち上がりをサポート、フレイル予防に貢献する。そして、立位が安定して筋肉の変動も少ないことから、ラクに姿勢を保持できる設計だ。また、利用者は残された筋力を日常的に活用することで、筋力や筋量が低下してしまう筋廃用や身体機能の低下を予防することもできる。JATCOはクルマの「走る技術」からひとを「支える技術」へと視点を広げ、精密制御・高品質管理のノウハウを福祉分野にも応用していく考えで、Lifmyは、介護されるひとと介護するひとの双方に寄り添い、移動の自由を支援する製品とされる。 使い方は簡単で、利用者はまずフットステップに足を乗せ、胸や脇のパッドに身体を預けて固定する。次に車輪をロックし、リモコンの「たつ」を押すことで、ゆっくりと立ち上がる。その後、両サイドのシート部を横にして「すわる」操作を行い、車いすに腰掛けた後に車輪ロックを解除し、移動を開始する。目的の場所に着いたら、再度車輪をロックし、リモコンの「たつ」で立ち上がらせ、「すわる」操作によって着座が完了する。 立ち上がりを科学する 「立ち上がりを科学することをテーマにしました」と語るのは、話を伺ったジヤトコ株式会社 介護機器事業室 プロフェッショナルスタッフ 津田聡彦さん。従来の機器は、被介助者の身体を抱えて、物のように持ち上げて移乗させるタイプだが、Lifmyは「立ち上がりたい」との本人の意思を自然なカタチでサポートすることがコンセプトになっている。また津田さんは「まだ残っている筋力を最大限に活かしながらラクに立ち上がれることを目指し、最も自然で負担の少ない立ち上がり時の身体の軌跡を再現しようとしています」と明かす。そのため、じつは立ち上がりのときと座る時の軌跡が異なっているという。立ち上がりの軌跡に沿って座ろうとすると、身体が後ろのほうに傾いて不安になる、といった体験者の声なども反映されている。 Lifmyは本体重量約27kgと軽量で、全長×全幅×全高が919mm×526mm×1021mmとコンパクトなサイズのLifmyは、入り組んだ施設内や、廊下・ドア周りなど家庭の狭い居住スペースでも取り回しが容易である。充電式リチウムイオン電池を搭載し、最大で約120回の移乗動作が可能とされる。また、身長140cm~170cm、体重75kg以下の利用者を対象としており、在宅・施設を問わず扱いやすい設計となっている。 単なる移動補助機器にとどまらず、自立支援と介助者の負担を軽減することを目指すLifmy。軽量設計やバッテリー稼働回数、幅広い対象利用者なども含め、現場導入のしやすさと安全性が追求されている。2026年初旬の発売が予定され、まずは介護施設向けに展開した後、医療・リハビリ分野への拡大も視野に入れている。また、JATCOの海外拠点に対して、その地域でのニーズや利用者の体格などについての情報集めも行なっているという。利用者の生活の質を支え、向上させることに直結する製品となり得るだろう。 ...
On 2025年11月22日 / By wpmaster文と写真●Believe Japan 2025/11/10(月)配信 日本最大の福祉機器展「H.C.R.(国際福祉機器展)」に今年も行ってきました! ここではヤマハが長年開発し続けている手動車いすの電動化ユニット、その30周年を祝う特別展示と最新モデルをレポートします。 追い求めてきた車いすの電動化 二輪車をはじめ、マリン製品や産業用ロボットなどを製造するヤマハ発動機は、1995年から30年にわたって「手動車いすを電動化するユニット」の開発を続けており、後付け可能な簡易型電動車いすのカテゴリーを確立してきた。ブースでは、初代モデルから現在に至るまでの技術進化の軌跡を体系的に紹介。鉛バッテリーからリチウムイオン電池へ、アナログ制御からインテリジェント制御へと進化してきた過程がよくわかる内容だった。 ヤマハは今後「ユニット専業メーカー」へのシフトを明らかにしており、ほかの車いすメーカーとの供給パートナーシップを強化する方針を掲げている。そんなわけで、松永製作所、日進医療器、ミキなど大手メーカーをはじめ、ヤマハの電動化ユニットを採用する多くのメーカーが紹介されていた。来場者は各社のフレーム設計や装着アレンジを間近で確認できた。 そして、長年にわたる開発の集大成として登場したのが、簡易型アシスト「JWX-2」と、フル電動「JWG-1」という2つの電動化ユニットである。どちらも、ほとんどの手動車いすのフレームに装着可能で、利用者の身体機能や生活スタイルに応じて選択できる新しい移動ソリューションといえる。ブースではこれらの試乗体験も行われ、多くの来場者がその進化を実感していた。以下、それぞれを紹介する。 自力走行を活かすアシストタイプ「JWX-2」 利用者がハンドリムを操作し自走する力に応じてモーターがアシストを加えることで、坂道や段差での負担を軽減しつつ自然な操作感を維持するというアシストタイプの電動化ユニットが「JWX-2」である。下り坂では自動的にスピードを制御して安全性を確保し、横に傾いた道では左右輪のアシストレベルを自動で調整して車いすがまっすぐ進むよう補正する。さらに、片方の手や足での操作であっても安定した走行を可能にし、坂道や不整地でも平坦な道を走行しているかのような感覚を生み出す先進の制御技術を備えている。これにより、日常生活での移動負担を大幅に減らしつつ、身体機能の維持にも寄与する。 JWX-2が対象とするユーザーは、日常的に自力走行を維持したい高齢者や筋力低下が少ない人、屋外での移動が多く坂道や段差のある場所にもよく出かける人である。なお、2025年4月1日からは制度改正により、手動車いすから電動車いすへの買い替え時には、原則として簡易型電動アシスト車いすへの移行が推奨されることになった。これは、完全電動では自力操作の機会が減少し、身体機能の低下が懸念されることから、アシストタイプを標準仕様として健康寿命を延ばすねらいがある。 JWX-2のユニット重量は15.6kg(バッテリー含まず)で、耐荷重は130kg。1充電でのアシスト走行距離は36km(リチウムイオンバッテリー)で、価格は補装具費支給制度価格で41万2600円(税抜)となる。 完全自走で自由な移動を実現する「JWG-1」 一方、主要部分を大幅にアップデートした「JWG-1」は、ジョイスティック操作による完全自走を実現したフル電動タイプ。自力操作が困難な人でも独立した移動が可能であり、ほとんどの手動車いすフレームに装着可能。生活スタイルに合わせたカスタマイズにも対応している。 ジョイスティックを中央に戻すと停止する電磁ブレーキを採用し、坂道などでも安心して操作できる。また、専用ソフトによりスピードや感度などを細かく調整することも可能である。操作部のディスプレイは1.7倍に拡大され、バッテリー重量も3.6kgから2.4kgへと軽量化。使い勝手や安全性が格段に向上している。 JWG-1のユニット重量は15.1~16.4kg(16~24インチ、バッテリー含まず)で、耐荷重は160kg。1充電での走行距離は25km(20~24インチ)で、価格は補装具費支給制度価格で39万3900円(税抜)となる。 さらに好評だったのが、ヤマハ製ユニットを使用するユーザーを対象とした無料点検サービス。バッテリー状態のチェックやモーターの点検のほか、技術スタッフによる個別相談も行われ、ユーザーサービスも積極的な一面を垣間見れた。 今回のブース展示は、単なる製品紹介にとどまらず、技術の進化と利用者の体験を融合させた空間であった。アシストタイプの「JWX-2」は自力操作を活かした快適な移動を実現し、フル電動タイプの「JWG-1」は完全自走による独立した移動を可能にする。それぞれが異なるユーザーのニーズに応える存在であり、ヤマハが30年にわたって積み重ねてきた電動化技術の結晶といえる。来場者は試乗を通して、その操作感や制御の精密さを直接体感し、両モデルがもたらす新たなモビリティの形を実感していた。 ...
On 2025年11月10日 / By wpmaster文と写真●Believe Japan 2025/11/3(月)配信 日本最大の福祉機器展「H.C.R.(国際福祉機器展)」に今年も行ってきました! ここではトヨタ ノア/ヴォクシーに新たに登場した「ショートスロープ」をレポートします。 現行モデルである3代目シエンタが登場した2022年7月、数あるビリーヴカー(福祉車両)のなかでも画期的といえる1台が加わった。それが「ショートスロープ」だ。このモデルは、車いすの乗り込み時間を大幅に短縮できることから、頻繁に車いすユーザーの送迎を行うデイケアサービスなどで大活躍すると期待がよせられてた。その後、予想どおりプロユースで重宝されることになったわけだが、同時に一般ユーザーの関心も大きく集めることになったという。 そして、今回ノア/ヴォクシーの一部改良(2025年9月2日)の際、「ショートスロープ」が加わったわけだ。対象となるグレードは「ノアタイプI、タイプII(サードシート付き)」、「ヴォクシータイプI(車いす1名仕様)」となる。 車いすを乗せるときに、30%ラクになった 今回ノア/ヴォクシーの「ショートスロープ」は、新たに2段折れのパネルを採用したことがシエンタとの違い。パネルを2段階に展開することによって、後端の高さを150mmにおさえることとなり、乗降時の介助者の負担をより低減することにつながっている。具体的には、スロープに前輪を乗せた後、後輪を乗せるときの力を30%ほど低減することに成功したという。 また、乗降時の作業を手動で行うことに不安なひとに対して、電動ウインチも装着可能(メーカーオプションで設定)。一定の距離をアシストしてくれる「自動モード」も加わった。さらに、リモコンを持ちながら車いす乗車を行う不安を解消するために「リモコンをホルダー」も追加。これはホルダーにリモコンを固定させることで、両手がふさがらずより安心して乗降作業をアシストすることができるようになった。 シエンタの「ショートスロープ」はトヨタとして初の試みであり、プロユースを想定していたが、思いのほか一般ユーザーからの問い合わせが多いことから、今回ノア/ヴォクシーにも車種を拡大したという。 ...
On 2025年11月3日 / By wpmaster文と写真●Believe Japan 2025/10/15(水)配信 欧州最大の福祉機器展「REHACARE(リハケア)」に今年も行ってきました! 今回は、最大270kgの耐荷重を誇る車いす「ECLIPSE Tilt(エクリプス・ティルト)」をレポートします。 会場を歩いていると、日本の製品とは雰囲気の異なる車いすが目に留まった。 太く堅牢なフレームと力強い足まわり、幅広の座面、そして黒を基調とした重厚なデザイン。それが、デンマークの医療機器メーカー COBI REHAB(コビ・リハブ) が展示していた「ECLIPSE Tilt」だ。ヨーロッパでは近年、体格の違いを特異なものではなく“自然な個性”として受け入れる考え方が広がっている。その流れの中で発展したのが、肥満・高体重者向けの医療・介護支援を指す 「バリアトリック(Bariatric)ケア」 だ。 この分野では「どんな体格の人も尊厳を持って生活できる」という視点が重視されている。そして、その思想を象徴する車いすがこのECLIPSE Tiltである。一般的な車いすの耐荷重はおよそ100~130kg前後だが、ECLIPSE Tiltはその2倍以上となる270kgに対応。体格が大きいことを理由に移動を制限されたり、窮屈な姿勢を強いられることがない。 デンマーク流の人間工学設計 COBI REHABは、高体重者や肥満患者のための医療・介護機器を専門に開発するメーカーだ。その設計思想の根底にあるのは、「ユーザーの尊厳を守ること」。ECLIPSE Tiltは、ただ頑丈なだけではない。背もたれと座面を独立して角度調整できる機構を採用し、姿勢保持の快適性に徹底的にこだわっている。これは単なるリクライニングではなく、座面の角度を変えることで体圧を分散し、呼吸や血流への負担を軽減する仕組みだ。また、シートクッションには通気性と耐久性を両立させた高密度フォームを採用。大柄なユーザーでも沈み込みすぎず、しっかりと安定した姿勢を保てる。長時間の着座や介助時の体位変換など、さまざまな場面でユーザーと介助者の双方が快適に動けるよう工夫されている。 実際に触れてみると、介助者側への配慮も随所に感じられた。ハンドルの高さは工具なしで調整でき、ブレーキレバーは大型でしっかり握り込める。フットサポートの高さ調整や取り外しも容易で、乗り降りの安全性が高い。さらに後輪のキャスター構造は、方向安定性と回転の軽さを高いレベルで両立。270kgのユーザーを乗せた状態でも、驚くほど軽やかに方向転換できるという。担当者によれば「重量に耐えるため剛性を上げると操作が重くなりがちですが、支点位置やタイヤ圧まで最適化しています」とのこと。... ...
On 2025年10月15日 / By wpmaster2025/10/11(土)配信 トヨタ・レクサス・GRの純正オプションを正規販売店で後付けできるサービス「UPGRADE SELECTIONS by KINTO」で、トヨタの福祉用品「いつでもウェルキャブ」の一部アイテムが、2025年10月8日よりウェブサイトで申し込みできるようになった。 これまで福祉用品のクルマへの施工は、トヨタ正規販売店での相談・申し込みが前提となっていたが、UPGRADE SELECTIONS by KINTO FACTORYでの取り扱い開始により、自身のPCやスマートフォンから気軽に相談や申し込みできるようになる。まずはシエンタで「ターンチルトシート(助手席用)」と「車いす収納装置」がウェブサイトから申し込みできるようになり、順次車種およびアイテムの拡充も検討していくという。 2025年10月8日現在の対象車両は以下のとおり。 ・シエンタ(2015年7月~2022年7月生産分)・シエンタ(2022年8月~2024年5月生産分) ターンチルトシート車とは? シート横のレバーを操作してシートを回転し、傾けることができる福祉車両のひとつ。両脚をそろえたままスムーズに乗り降り可能なため、高齢の方や足腰に不安を抱える方などに最適なモデル。 車いす収納装置とは? スイッチ操作で折りたたんだ車いすを電動で収納できる装置。主に35kg以下の車いすに対応しており、使用しないときは後付け装置を取り外してラゲッジルームを広く使うことができる。車いすの積み下ろしの負担を軽減できるのが特徴である。 ...
On 2025年10月11日 / By wpmaster文と写真⚫︎Believe Japan 2023/10/17(火)配信 「行きたい、のそばにトイレが行きます」というキャッチフレーズが新鮮な、トヨタの「モバイルトイレ」。ありそうでなかったこの移動式トイレは、普通免許でけん引でき、必要とされる場所にコンパクトに設置できる画期的なトイレだ。予期せぬ災害時はもちろん、お祭りや花火大会などのイベント、キャンプ場やリゾート地、医療的ケアが必要な方が在籍する学校や施設など、その役割の範囲は想像以上だろう。 上下水道と直結可能な水洗トイレということで、なかの様子はさながら一般的な建物のバリアフリートイレそのもの。一見すると普通のトイレなのだが、便座や手すり、ゴミ箱や緊急ランプなど、日本製らしいきめ細やかな設計はさずが。これなら海外でもウケるのではないかないかと思った。 ...
On 2023年10月17日 / By wpmaster文と写真⚫︎Believe Japan 2023/10/16(月)配信 トヨタブースでは、電動車いす「JUU(ジェイユーユー)」の実演が行われた。昨年の国際福祉機器展(H.C.R.2022)で披露された新時代の電動車いすだが、今年も進化して会場にやってきていた。このJUUの特徴は、乗り降りを安全にアシストしたり、階段、段差、急勾配など、一般的な車いすが通ることが難しい場面でも使えること。このフレキシブルな走破性能は、車いすに圧倒的な自由度を与えてくれる。 実演では、シエンタの福祉車両からJUUを下ろすところから始まった。車体に積まれたJUUは、タブレットからワンタッチで自動でスロープを降りてくる。JUUの後部には「しっぽ」が取り付けられ、これによって段差でも衝撃がなくスムーズに降りられる。役目をおえた「しっぽ」は、自動的に迫り上がって格納されるため、乗員には一切の負担はない。その後、スロープを降りたJUUは、自動で運転席の横まで自走してやってくる。さらに車いすに移乗しやすいように、シートが自動で変形するのも見どころ。まさに至れり尽くせりだ。 次は段差を乗り越えるシーンを実演で再現。近年バリアフリー化が進んでいるとはいえ、当然すべての場所がそうなっているわけではない。今までなら諦めたり、だれかの手を借りなければいけないシーンもJUUなら障壁を超えられる場面が多い。ちなみに段差を登る際も、前述の「しっぽ」が活躍する。車体が「しっぽ」に支えられるため、前のめりになったり後ろに倒れないから安心なのだ。凹凸のある下り坂も、径の大きな車輪とオフロードタイヤのおかげで安定して進める。 電動車いすは、小まわりが効かなそうなイメージを持つかもしれないが、JUUは異なる。その場で回転するように動けるので、狭いスペースでも簡単に方向転換できるのも大きな特徴。そのほか、手持ちのタブレットでJUUの状況がわかったり、遠隔で操作もできる。これは車いす利用者だけではなく、介助者にとっても大きなメリットになるはずだ。 現在はまだ商品化されていないが、これが実現すれば多くの人に移動の自由が得られる。これは、もっともっと人生を楽しみたい気持ちを後押ししてくれるもの。JUUの発売が待ち遠しい。 ...
On 2023年10月16日 / By wpmaster2022/4/22(金)配信 ダイハツは福祉介護・共同送迎サービス「ゴイッショ」を、2022年4月22日に発表。全国の地方自治体を対象に販売を開始する。 このサービスは、複数の介護施設の送迎業務を外部委託し、地域全体で共同化することで効率のいい送迎を実現。これにより、介護施設の人材不足の解消が可能になる。「ゴイッショ」の導入で介護施設は送迎以外の業務に注力でき、コスト低減にも寄与。結果として、地域全体での介護サービスの高品質化にもつながるという。 サービス提供にあたっては、より地域に根ざしたサービスとするべく、課題調査、実証実験の企画・運営を地域と連携して行い、導入決定後は運行管理システムの提供や運営を支援する。さらに、送迎の空き時間を活用した「買い物支援などの移動サービス」、「宅食サービスなどモノの配送」など、ほかのサービスとも掛け合わせた取り組みについても検討支援を行う。 ダイハツが福祉介護・共同送迎サービス「ゴイッショ」公式サイトhttps://www.daihatsu.co.jp/goissho/ ...
On 2022年4月22日 / By wpmaster文●石井昌道 写真●Believe Japan 2022/1/12(水)配信 翔(KAKERU)はホンダの最新車いすレーサー(陸上競技用車いす)。いかにも競技用といった無駄のない機能美に目を惹かれるが、ここにたどり着くまでには長い歴史があった。 1981年に障がいのある人たちの社会的自立の促進を理念としてホンダ太陽(本田技研工業の特例子会社)が設立され、そこに所属する障がい者スポーツのトップアスリートによって1999年にホンダアスリートクラブが発足。翌年には本田技術研究所が車いすレーサーの開発に取り組み始めた。2002年からは毎年新しいモデルを投入して競技を続け、2013年には八千代工業が参加することで量産体制が整う。2014年の極(KIWAMI)、翌年の挑(IDOMI)などを経て、20年の集大成となったのが翔(KAKERU)なのだ。 ウイング形状のメインフレームやホイールなどフルカーボン製で、直進性を保つステアリングのダンパーをフレーム内に収めたビルトイン・ダンパーステアリングが特徴。ルックスも美しくなり、グッドデザイン賞を受賞している。価格は383万円(塗装あり/税別)とプレミアムコンパクトカー並みだ。 今回試乗させてもらったのは前モデルの挑(IDOMI)で、ビルトイン・ダンパーステアリングではないものの、バリバリの競技用で貴重な体験だった。まず、注意深く乗り込む必要がある。胸が太ももにぴったりとくっつくぐらいの前のめりの姿勢でバランスするようにできているため、普通に起き上がった姿勢で腰掛けると簡単に後ろにひっくり返るからだ。 ただ走らせるだけなら、それほど難しいことはない。一般的な車いすと同じようにホイールのハンドリムに手をかけて回せばいい。ただし、発進時にはハンドリムはかなり重く感じる。速く走るために、少ない操作でもホイールがたくさん回るようハンドリムが小径だからだ。発進してある程度まで速度がのってくると快適。さすがは競技用で走行抵抗が少なく、惰性で気持ちよく転がっていく。自分なりに感じたコツとしては、ハンドリムを操作するときは、短いストロークのなかで一気にトルクをかけること。こうするとグンッとスピードアップが図れる。ステアリングはダンパーによって直進状態が保たれるようになっていて、惰性走行のときに進路修正を図りながら進んでいく。 腕が疲れるのはもちろん、進路を見るために頭を上げるから首も疲れる。前のめりの姿勢を維持するのも意外や大変で、これでマラソン競技をするアスリートをリスペクトする気持ちが生まれた。それでも、信じられないほど軽量・高剛性で走行抵抗の少ない本物の競技用車いすレーサーを走らせることは、この上なく気持ちいい体験だった。プロの道具の凄さを知って贅沢な気分になれたのだ。 自動車ジャーナリスト 石井昌道 内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)自動運転にも参加する自動車ジャーナリスト。幅広い視野と知見で的確な評論を行う。 ...
On 2022年1月12日 / By wpmaster© 2016-2020 Believe Japan, Inc. All rights reserved.